 |
 |
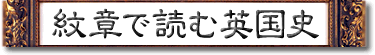 |
| 丸屋 武士(著) |
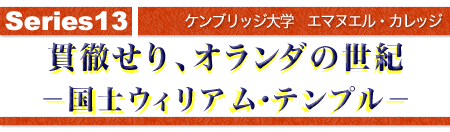 |
 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
国王ジェームズの宮廷に仕えて、権力のおすそわけ(政治)に与っていたイギリス貴族や大司教達はしぶとかった。年を越しても自分の立場がはっきりしないウィリアムは内心苛立ってはいたが、例によって無関心を装い続けた。1689年1月22日開会したイングランド仮議会は、1月28日に至って、ジェームズが退位し、王位が空白になったとの議決を採択した。しぶといイギリス人達は、強力なオランダ人ウィリアム3世に大きな力を与えたくないというのが本音で、王位を誰にするかが決まらぬまま小田原評定を続けた。この間、ダンビーはウィリアムの妻メアリー(ジェームズ2世の長女)に手紙を書き、メアリーが望むならばイングランド議会にメアリーを単独の君主とすることを承認させる、と誘った。これに対してメアリーは憤然として、自分と夫の利害を分かとうとするのはこの上ない薄情なことであり、自分は何事につけ夫と共同し、夫に従う、とダンビーに書き送り、その手紙の写しとダンビーからの手紙をウィリアムに送った。とうとうウィリアム3世お得意の戦法を用いる時がきた。1689年2月5日、ウィリアムはスチュアート朝の重臣とでもいうべき初代ダンビー伯爵トーマス・オズボーン、初代ハリファックス侯爵ジョージ・サビル、第7代シュルーズベリー伯爵ギルバート・タルボットを呼び出した。3人に向かって、ウィリアムが補佐的な役割としての摂政の地位に就いたり、女王(妻メアリー)の単なる夫になるつもりはない、イギリス人がそういう了見ならばオランダに帰って、今後一切イングランドから手を引かせてもらう、と恫喝した。これで決まりであった。オランダ人ウィリアム3世がイングランド国王に就任することになった。オランダを出発する前に、イングランド貴族からの文書による連名の招請状を取り付けた上で、500隻余の無敵艦隊に2万1千もの軍勢を率いて乗り込んで来た用意周到、歴戦の強者、ウィリアム3世は、イングランドを侵略したとか、王位を簒奪したという印象を与えないよう、おとなしく構えていただけであった。20万を越える常備軍を持って、戦争に「栄光」を求めるというよりは戦争を「生き甲斐」とし始めたルイ14世を阻止し、祖国オランダを救うための「起死回生」の策として、英蘭の軍事的合体が不可欠であった。一方、英蘭を核とする勢力を結集して、フランスの力を殺がないことには、イギリスの安全もあり得なかった。これが「名誉革命」と称される「事変」の実情であった。 |
|
|
 |
| しかしながら、オランダという国家の本質をなす「底の深い輝かしい文明」も、間もなくその存亡の時を迎えるに至った。オランダ連邦共和国の舵取り役デ・ウィットの背後から大波が押し寄せ、デ・ウィットは波にのみ込まれて海のもくずと化し、オランダという国はほぼ沈没という状況に陥ったのである。絶体絶命とでもいうべきオランダ衆民の願いと期待に応え、命を捨てて(決死の覚悟で)祖国を不条理な専制から護ったのが21歳のオレンジ公ウィリアム3世であった。民衆に八つ裂きにされた上、刻まれた体の部分を高額で売り飛ばされたデ・ウィット、父祖伝来の総督という地位と共にお先真っ暗な祖国を背負い込んだウィリアム、この二人に深く信頼され、厚い友情を育てながら、義務を重んじ、感情にとらわれず、毅然として運命を甘受したウィリアム・テンプルの一生があった。遠回りをしたが、次回そのことをお話ししたい。(シリーズ14に続く) |
 |
 |
ケンブリッジ風景 (2004/12撮影) |
 |
|
| (2005年3月) |
 |
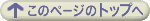 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |