 |
 |
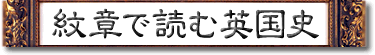 |
| 丸屋 武士(著) |
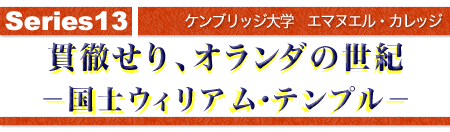 |
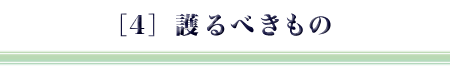 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  |
 |
 |
エマヌエル・カレッジ裏庭 (2004/12撮影) |
 |
|
| ところで、アメリカ合衆国駐英大使は大抵大金持である。典型的にはケネディ大統領の父ジョウゼフ・ケネディがそうであったように、大統領選で大きく貢献(献金その他)した人物に大統領が論功行賞の一環として行う人事が駐英アメリカ大使のポストである。17世紀も終わりに近いヨーロッパにおける大使の地位も現代の官僚制におけるそれとは様相を異にしていた。平和が回復して駐ブリュッセル公使であったテンプルに駐ハーグ大使の話が来たのは喜ぶべきことのようであるが、事態は官僚制の中での栄進というような単純な問題ではなく、特に金銭面の問題が多々あってテンプルはすぐには応諾しなかった。公職(官職)を金銭で売買するこの時代の悪習(買官制)については後に改めて言及したい。結局1668年8月下旬ハーグ駐在イングランド大使となったテンプルはロッテルダムの港に上陸した。その日の夜には召使いを一人連れただけで簡素な馬車に乗って非公式にデ・ウィットを訪問した。翌日オレンジ公ウィリアムに面会を申し込むと、翌々日には会見が実現した。この時からほぼ2年の間、ルイ14世とイングランド国王チャールズ2世との秘密取引によってテンプルが外交の舞台から外されるまで、テンプルとデ・ウィット、テンプルとオレンジ公ウィリアムとの信頼と友情は深厚なものとなっていった。オランダの国運を左右した二人と同時進行でそのような関係を構築できた大使テンプルの働きは正に、三軍の将以上のものであった。 |
 |
 |
エマヌエル・カレッジ教授宿舎 (2004/12撮影) |
 |
|
| 37歳にして外交官(駐ブリュッセル公使)となって5年のうちにプロテスタント三国同盟の締結という大仕事をしたテンプルは類まれな資質を有する人物であった。後世、特に日本において知られているような、文筆家(散文の名手と呼ばれる)としての一面からは想像もできない行動力と克己心の持ち主であった。行動は迅速果敢、物事の本質に迫る本能にすぐれ、疲れを知らぬ行動力と粘り強さを持つ一方、驚くほど率直かつ誠実な人物であった。テンプルは外交交渉という微妙な場においてさえ、まぎれもない卒直さをもって臨み、意欲的で快活な気性(多血質)によって、官僚的儀礼や形式主義を押しのけても大した怨みは買わなかった。通り一遍の儀礼には全く無頓着でありながら、相手を包み込むような人間的魅力に溢れ、抜群の説得力を発揮した。穏健中庸を旨としつつも、一人でも立つ気概を持った、買収不能の廉直豁達の士であった。このような類まれな人物を英国大使として迎えたオランダこそ幸運であったと言うべきであろう。重商主義の権化コルベールが収奪する富に支えられて、王権神授説の体現者、カソリックの守護神ルイ14世がヨーロッパを蹂躙するのを阻止せねばならない。それにはプロテスタント国同士の英蘭が同盟すべきである。そう信じるテンプルは「勢力均衡策」の相手国オランダに対して、単なる戦略的パートナーとしてではない親愛と賞賛の念を抱いていた。「政治的自由」と「信仰の自由」とを基軸とする底の深い輝かしい文明の母体であるオランダという国の美点(長所)として、テンプルの指摘する事項の全ては、人類が永遠に追求し、護るべき、普遍的価値を有するものであった。21世紀の今日に至ってもテンプルが称賛する諸事項の半分も実現し得ない国々が大多数であることを思うと、17世紀オランダの達成した文明は、まさに「世界史の奇跡」であった。 |
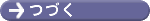
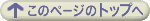 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  |