 |
 |
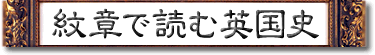 |
| 丸屋 武士(著) |
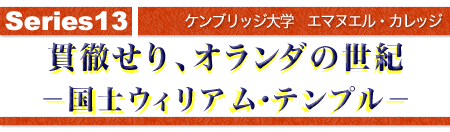 |
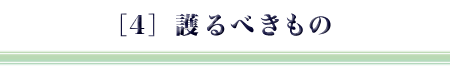 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  |
 |
 |
ハーグ市 ビネンホフ宮殿 (2004/12撮影) |
 |
|
今ここに、テンプルが挙げるオランダ連邦共和国の有する美点を、敢えて箇条書きにして列挙したい。
- 志操堅固で勇気がある
(constancy and courage)
- 勤勉で質素である
(industry and frugality)
- 困難に負けずがんばり通す気力がある
(perseverance)
- 公徳心が高い
(public spirit)
- 貴族等支配層が威張ることがない
(freedom from ostentation of their nobles)
- 慈善施設(特に病院)が賞賛に値する程整っている
(admirable organization of charities)
- 規律と厳密さが行き渡った商慣習
(order and exactness in managing their trade)
- 国としての信用を常に高く保つために、国家財政をたくみに運営している − 健全財政の堅持
(excellent administration of public finances so that the credit of the state is always high)
- 宗教的寛容のシステムが定着している
(their system of religious tolerance)
|
 |
 |
ハーグ市 ビネンホフ宮殿 (2004/12撮影) |
 |
|
| 以上諸事項を総括すると、資源に乏しく気候に恵まれない風土によって、オランダ人は絶えまなく働き続け、贅沢と虚栄を排して節倹に努めねばならなかった。個人にとっても国家にとっても、収入よりも少ない額を消費することによってのみ富は生ずるものであることが、広く深く認識されていた。そのような思考用式の中で、シリーズ11で言及したようにイギリスに上陸したオランダ遠征軍18個連隊のうち、10個連隊はオランダ連邦議会が、5個連隊はウィリアム3世がそれぞれ費用を分担していた。オランダ人にとっては戦争もワリ勘(オランダ勘定)でやるべきものであった。そして、専制が罷り通っていたこの時代のヨーロッパにおいて、信仰の自由(宗教的寛容)と政治的自由とを確立した底の深い文明は、合理的精神の高揚によって国際法や近代哲学の基礎を生み出した。単に節倹に努める(悪く言えばケチ)ばかりでなく、現実に即した着実な実践力を展開する国民性は、精密科学や解剖学、臨床医学、数学や物理学に輝かしい進歩をもたらした。テンプルは妹マーサと初めてオランダを訪れた時、オランダ人が最も重んじている政治的自由の実態にふれて驚愕した。公(おおやけ)の事柄について人々が何の遠慮もなく、あらゆる事を真剣に議論していたのであった。日本でそんな事をすれば当然打ち首獄門であり、ピョートルが君臨するロシアは言わずもがな、スペイン、フランスにおいても投獄あるいは鞭打ちは免れないところである。ハーグの町では国家の最高責任者デ・ウィットやオランダ海軍の最高責任者デ・ロイテル提督がお供も従えずに一人でテクテク歩いている姿がよく見られたという。他の西洋諸国のように国王や貴族あるいは高位聖職者が自らの勢威を示すために行う行列(行進)のようなものが、オランダには一切なく、国政の最高責任者デ・ウィットの召使い(従僕)は、たったの1人であった。テンプルは突出する軍事大国フランスに対する「勢力均衡」の単なる戦略的パートナーとしてではなく、オランダという国の本質を心から称揚していたのであった。 |
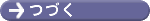
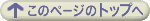 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  |