 |
 |
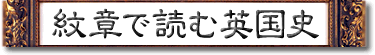 |
| 丸屋 武士(著) |
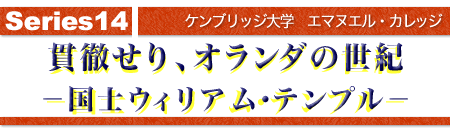 |
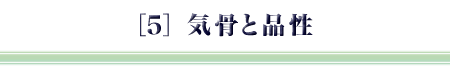 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 1628年(寛永5年)ロンドン市内で生まれたウィリアム・テンプルは1648年、ケンブリッジ大学エマヌエル・カレッジを卒業しないまま、当時の大学卒業者としての風習(紳士教育の総仕上げ)にしたがって大陸遊学(Grand Tour)に出発した。途中ワイト島で機智に富む1歳年上の美人ドロシー・オズボーンと知り合い、特別の感情を持った。大陸ではパリに2年滞在したテンプルはフランス語を習得し、その後オランダ、ドイツ等へも旅行をしたが主としてスペイン領ネーデルラント(ブリュッセル)に留ってスペイン語もマスターした。既に大学進学前のグラマー・スクールにおいてテンプルは読み書きばかりでなく会話を含めたラテン語もきっちり習得していた。これらの語学能力が後年彼の外交官としての働きに大きく役立ったことは言うまでもない。ワイト島で知り合ったドロシーは引く手数多の花嫁候補であり、花婿候補の中には護国卿クロムウェルの四男や、ドロシーの従兄弟でもあり後にダンビー伯としてイングランド政界の中心人物となったトーマス・オズボーンらがいた。ドロシーの兄弟に好かれていなかったテンプルは7年間誠実に文通を主とする交際を継続した。そのうちドロシーは不幸なことに天然痘に見舞われ、顔にあばたが出来てしまったが、結局7年間の誠意が実ってテンプルは1655年ドロシーを妻とすることができた。結婚した二人はテンプルの父の荘園があるアイルランドへ渡り、テンプルはアイルランド地方議会の議員を務めるかたわら、7年間哲学と歴史の勉強に集中した。その研鑚や晩年の著作から判断して、エマヌエル・カレッジにおける訓詁注釈的学問は「多血質」で「生気に溢れる」テンプル青年の心を捉えるに足る程のものではなかったと思われる。本シリーズ2でも紹介したように、イギリスで最も偉大な天文学者であり、当時の科学者としてニュートンに次ぐ人物であるとされているエドモンド・ハレーは1673年オックスフォード大学クイーンズ・カレッジを卒業しないままセント・ヘレナ島への観測旅行に出発してしまった。『ローマ帝国衰亡史』の著者エドワード・ギボンは1752年から翌年にかけて14ヶ月、オックスフォード大学モードリン・カレッジで学生生活を送ったが後に彼は、モードリンでの生活は生涯で最も怠惰で空虚な生活であったと回想した。エマヌエル・カレッジについては後に付言したい。 |
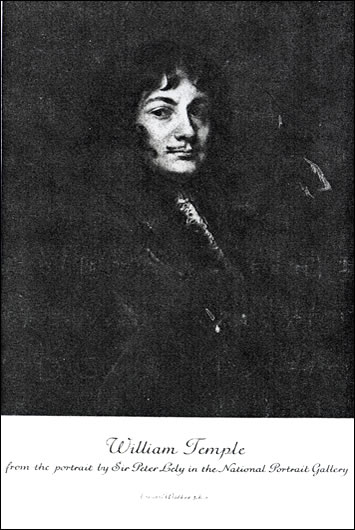 |
 |
テンプルの肖像
『SIR WILLIAM TEMPLE』
The Man And His Work
BY
HOMER E.WOODBRIDGE
KRAUS REPRINT CORPORATION より |
 |
|
| 話を元に戻すと、ウィリアムとメアリーの縁談についてはテンプルの妻ドロシーが一働きすることになった。とりあえずはウィリアムに対してメアリーの人となりに関する情報を提供する役目をドロシーが担当した。きっすいの王党派の一家に生れたドロシーの人脈が生かされて、ドロシーが集めたメアリーに関する情報は極めて芳しいものであったが、さすがというべきか、ウィリアムはどんなに良い情報を得ても実際にメアリーに面会するまでは結婚に踏み切らなかった。 |
| 1677年7月5日、戦争を続けているフランスと同盟側(オランダ、スペイン等)との講和会議の調停役としてナイメーヘンに滞在していたテンプルは、国王から突然召換された。妻子を残したまま一時帰国をしたテンプルに対して国王チャールズ2世は宰相(Secretary of State)への就任を要請した。この時を含めてテンプルには生涯に3度宰相就任の話があったが、そのいずれの機会も逸することになった。国家(国王?)にとって重要な役職(公職あるいは官職?)を金銭で売買するというこの時代の悪習(買官制)をテンプルは唾棄しており、その渦の中で話が立ち消えになったり、今回のようにテンプルが辞退したり、いずれにしてもテンプルが宰相の地位に就くことはなかった。当時のイングランド政界の実情や、この後も続くナイメーヘンの講和を巡っての英国内外の動きについての説明は省略し、話をウィリアムとテンプルとの係わりに絞ってシリーズ14をクローズとしたい。 |
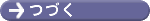
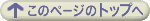 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |