�@
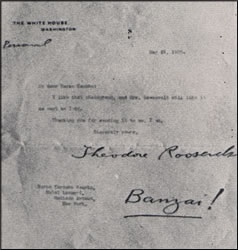 ��V���폟�����j�����q�����Y���ēd����
��V���폟�����j�����q�����Y���ēd����
���[�Y�x���g�́u�o���U�C�I�v�ƋL��
�i�������`���w���I�푈�Ƌ��q�����Y�x
�i���a55�N�V�L�����j���j
|
�@���R���Ȃ��i�H�j�J���^�S��łڂ��Ă��܂������[�}�鍑�̗��������܂ł��Ȃ��A21���I�̍����ɂ����Ă����ێЉ�̌����́u�ŎZ�ƕs�𗝂̉��s�v�Ƒ������邱�Ƃ��ł��悤���B���[�Y�x���g�͎Љ�s���ɗh�炮�鐭���V�A���S�ʓI�ɕ��Ă��܂����Ƃ��ł��|��Ă����B�����Ȃ���[���b�p�̐��͋ύt�͍��ꂩ�����ăA�����J���O���ɑ���e��������m��Ȃ�����ł���B�����ɁA�n���C�����A�t�B���s����̗L����A�����J�ɂƂ��āA���{���ߑ�ȗ͂��������ɑ���A�����J�̌��v��N���悤�Ȃ��Ƃ͍ł��]�܂Ȃ����Ƃł������B�����A�����I�����E�̒��S�ł��������[���b�p�̌`���͂ƌ����A�h�C�c�͕����푈�i1870�N�j�ɏ����Ĉȗ��u�t�����X�̕��Q�v����ɋ���āA�O�铯�����̑��t�����X�Ǘ���������琄�i���ă��V�A�Ɍ����ꂵ�ė����B1887�i����20�j�N�ɂ̓��V�A���̖�60%��ۗL����ő�̑ΘI�����ƂȂ����h�C�c�ł͂��������A�����Ƀh�C�c���Z�s��ł̓��V�A�̍��ٍϔ\�͂��^�������o���ƂȂ����B�����������邤���Ƀh�C�c�́u�����ƓS�v�̂��߂̐g����ȕی�ł��߂���o�ϓI�Η��𒆐S�ɓƘI�͐����I�i�n���w�I�j�ɂ��S�ʓI�ɑΌ��Ɋׂ�A�����̊W�͊J��̐��ˍۂɂ܂ň��������B��������Ă����t�����X��1887�i����20�j�N�A�p���Ńt�����X�̋�s�Ƀ��V�A�s������p�ӂ����邱�Ƃ����V�A���{�ɓ`�����B�����I�����Ԏ��ɚb�����V�A�Ɏ�������ׂ̂��t�����X�͘I������������A���ʂƂ��ăh�C�c�͐푈�ƂȂ�ΘI���������狲�����ɂ����댯�������Ă��܂����̂ł���B�Ђ�t�����X�����̓t�����X���Ǘ�����E�o�����Ă��ꂽ���������V�A�����h�̕ۏ�ƂȂ��Ă���鍑�Ƃ��Ċ��}���A���Ń��V�A���w�������B�����A���I�J���9�N���O��1895�i����28�j�N�ɂ̓t�����X�̐V���e�����u���V�A�̉ߏ�v�ƃ��V�A�̐M�p����Ƃ��āA���{�Ƀ��V�A�ւ̖�˕������߂�L�����y�[���鎖�ԂɎ������B����قǃ��V�A�̑t�����X���͒��ꂠ�����Ă��܂����̂ł���B�h�C�c�Ƃ͑a���A�����ȊW�Ɋׂ���A�t�����X�Ǝ��g�ނ��ƂŃ��[���b�p�ł́u�댯�ȌǗ��v������������V�A�́A���̔���ȑΊO�������̂��́A�V�x���A�S����}��Ƃ���ɓ��ւ̒鍑��`�I�i�o�̖�]�������Ē��߂悤�Ƃ͂��Ȃ������B
�@����A1805�N�̃g���t�@���K�[�C��Ńt�����X�͑������ł��Ĉȗ��A�r�N�g���A�������C���h�c����������A���̊C���x�z���鐢�E�鍑�Ƃ��āu���h����Ǘ��v��ۂ��ė�����p�鍑���A���̘I�������͂Ȑ��E�ő�̕������V�A�̓쉺����ɒP�Ƃł͎����������Ȃ��Ȃ����B1902�i����35�j�N1��30���A�u���h����Ǘ��v���̂Ă��C�M���X�́u���p�����v��������A���̓��p�������j���ē��{�ł͘A���̂悤�ɒ���������Ă̏j���Â��ꂽ�B�����̃����h�����w���̉Ėڟ��͊x���ɂ��Ă��莆�̒��Łu�����������̌�A�{���ɂĂ͔��ɑ�����悵�A�����̔@�����ɑ�����́A���i�������j���n�l���x�ƂƉ��g����茋�т���������̗]��A�����ۂ�@���đ��������܂��l�Ȃ���̂ɂ���͂�v�ƌ������B���̐��U�ōł��s�����Ȏ��Ԃ��߂����������h���ŁA���ɂ̓m�C���[�[�ɜ���Ĕ����̉\�����{�����ɗ��ꂽ�����Ȕh�����w���Ėڟ��́A���ێЉ�ɂ����ē��{���u����Ă��闧����O�Ɋώ@���Ă�����l�Ƃ����悤�B
�@�Í������A���i�o�ϗ́j�Ɨ́i�R���́j�Ƃ��߂���W�͕ϓ]��Ȃ��A���G����A鳖��鲁A��b���U�̃I�����_�b�i�V���[�Y10�`15�j�ł��b�����悤�Ɂu���̂��̗F�͍����̓G�v�ƂȂ�̂���ԂƔF�����ׂ��ł��낤���B�g���r�ɖ��g�����������Ƃ����}���ʂ�́u�O�����v�Ƃ����ς��������܂���Ĉȗ��A���{���{�͕K���ɂȂ��āA�u�����ɓȏ�̉��B��G�ɉʊO�𐭍�v��͍����������B�Ƃ��낪���I�푈�ɏ����A�J�������đ�1�����E���̐폟���ɂȂ��������肩��A���{�������u��Y����v�Ɋׂ��Ă��܂����B��l�B�̋��J���Y�A�u�g�̐k����悤�ȋْ��v�A�u�g���ł����s���v��Y��A遖��̕��������ɂ܂������B�u���������̔߈��v�A�u���鐣�����ߕ��v�ɑ��锽�������������������������̂ł��낤���B�u��Y����v�̍s������́A�u�Ǘ����v�Ɓu��@���̌��@�v�ł���B���Ƃ��܂߂ĉ�Ђ��̑������Ȃ�g�D���u��@���v�������Ă͕��邱�Ǝ����ł���B���������đΉ�����Ƃ����ԓx�������ɂ͖�������ł���B
�@���I�u�a��c�̊J�n������Ɏ��闼���S���c�̋��X���X�̋삯�����͋g�������̖���w�|�[�c�}�X�̊��x�ɏڂ����B���̏��_�ł͂����ɂ͗������炸�A���̍u�a��c���O�ɒ���A���₵�ĐV���卑�A�����J���O���̍��ƂƂ��Ă̈АM�݂̂Ȃ炸�A�哝�̌l�Ƃ��Ă��傢�ɈАM�����߂��Z�I�h�A�E���[�Y�x���g�Ɠ��{�Ƃ̊ւ��ɍi���Ă��b���������B����͓��{���O���ȑA�����J���O�������Ȃ��邢�͎��@�Α哝�̊��@�Ƃ����������̃��[�g��ʂ��ďo���オ�����W�ł͂Ȃ��A�S��������A����̂ɂ������͖���Ƃ�������ɂ߂Čl�I�ȊW�ł������B
�@���ɂ��̎���̃A�����J���O���͓�k�푈�̏��������ċ}���ɍH�Ɖ��A�s�s�����i�ݍH�Ɛ��Y���̓C�M���X���Đ��E�̎�ʂɗ����Ă����B�n���C�����A�Đ��푈�̏����ɂ���ăt�B���s�������̗L�A�Ԃ��Ȃ����̑吼�m�͑��͐��E����̍q�C�ɏo����\�͂ƗE�p�𐮂��������B���[�Y�x���g�����̂悤�Ȗu�����̍��O���哝�̂Ƃ��ċɓ��̐��͋ύt��}��Ƃ����n���w��̌v�Z�̒��ŁA�L���X�g�����i�������H�j���V�A���͋ɓ��i�Ⓦ�j�̏������{�ɐS���Ă����̂ɂ́A�[���A�傫�ȗ��R���������B���[�Y�x���g�����{�ۛ��ƂȂ����傽��v���Ƃ��Ď��̌܂̗v�����w�E�������B
- �����k�ւ�ɑ�\�������{�̔��p�H�|�ɐ��ʂ������łȂ��A�L���X�g���k�ł���Ȃ��牀�鎛�i�O�䎛�j�̗��@�A�@���@�̈�苗�����h���t�ɋA�˂����r�Q���[�A�t�F�m���T���l�Ƃ̌��ہB�Ƃ�킯�݂��Ƀt�@�[�X�g�l�[���ŌĂэ������x���r�Q���[�Ƃ̏I���ɘj��[����F�W�B
- �u���ُ_���B�i�_�p�ł͂Ȃ��j
- �݊w���Ɋ�����킹�����Ƃ͂Ȃ����A�n�[�o�[�h��w�������Ƃ��Ă̋��q�����Y�Ƃ̕��ʂ���Ƃ���15�N�ɏ���ہB
- ���q�����E�����V�n�ˈ�̖����wBushido:The Soul of Japan�x�ƃC�M���X�l�C�[�X�g���C�L�́wHeroic Japan�x��2���̏����B�w���m���x�̓m�C���[�[�ɜ��D�y�_�w�Z�i��̖k�C���鍑��w�j������ފ������V�n�ˈ���a�C�×{�̂��߂ɍȃ��A���[�E�G���L���g���̕ꍑ�A�����J�ɑ؍ݒ��p���ŏ�����A���{�ł͖�������Y�i��ɓ��呍���j�̖|��ɂ���Ċ�g���X����o�ł��ꂽ�B
- 15�N�O�Ɍ��@�z���A�鍑�c���ݒu���āA�ꉞ�������̌`�𐮂������{���ALiberty�i���R�j�AIndividualism�i�l��`�j�Ƃ���������`�̓�̍��������m�����A�������Ƃ��čs������悤�ɂȂ�A�Ƃ������[�Y�x���g�̕��������ҁB���[�Y�x���g�̊��҂̍����͐V���{������4�N��������~�����Ƃɂ���ĕ������x��@���Ƃ������j�I�p�f�������ċߑ�I�R�����m�������X�s�[�h�ɂ������B���̓��e���L�q������������L�C�[�X�g���C�L�́wHeroic
Japan�x�ł���B
�ȏ�5�̍��ڂɂ��Ď���ɘj���Ă��b�����Ȃ���A�ߑ㍑�ƂɂƂ��č��͂Ƃ͉����Ƃ������Ƃɂ��ĉ��߂čl���Ă݂����B
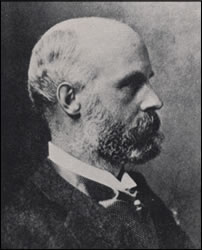 ������w��w�������Ƃ��ė��������r�Q���[
������w��w�������Ƃ��ė��������r�Q���[
�i�������`���w���I�푈�Ƌ��q�����Y�x
�i���a55�N�V�L�����j���j
|
�@ |
|
|