 |
 |
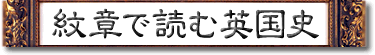 |
| 丸屋 武士(著) |
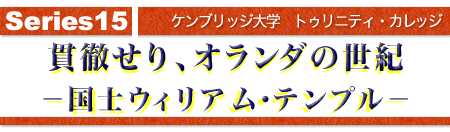 |
 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

ケンブリッジ大学セント・ジョンズ カレッジ
中庭と背後にそびえる礼拝堂
(2004/12撮影) |
| シリーズ1(1頁、5頁)、シリーズ12(8頁)で紹介したように、セント・ジョンズ カレッジ門楼は「イングランドの紋章装飾の白眉」と称賛されている。人通りの多いセント・ジョンズ通りからこの門楼を一歩入ると眼前にこのような光景が展開する。礼拝堂と台所や食堂と居室(寝室)を組み込んだ校舎が一体となった環境における日本人には全く馴染みのない3年間のカレッジ(学寮)生活がいわゆるオックスブリッジでの生活である(シリーズ9参照)。召使いを従え、門限を破って壁をよじ登るような学生の話は昔のことである。 |
|
さて、「大勢に抗することをものともせず一人でも立つ勇気」と「篤い信仰」によってウィリアム3世が命を捨てても護ろうとしたものを我々は今こそ、よくよく吟味すべきである。自分の命を保証してくれる英仏の申し出を言下に撥ねつけ、衆民から寄せられた信頼と期待を裏切ることなく、ウィリアムが命に換えても護ろうとしたものは、武将としての名誉であるとか、武門の意地といった類のものではなかった。生まれてから20年近くの間、祖国オランダを牛耳っていた人々は、デ・ウィットを先頭にウィリアムを排斥し続けて来た。陰に陽に、ウィリアムの政治的影響力に掣肘を加え続けたのは共和派(議会派)と呼ばれる人々ではなかったか。だがウィリアムは、王権神授説の体現者ルイ14世やその従兄弟チャールズ2世のように専制を縦(ほしいまま)にする者に征服された国土の君主として生きるよりは、「自由な共和国」の総督であり続けることを、自らの命を賭けても選んだのであった。ここにウィリアムの歴史上前例がないとも言える「貴重な決断」があった。イングランド侵攻に際してウィリアムが英国臣民に与えた宣言書にも明らかなように「あらゆる人々を信条を理由とした迫害から守ること、そして国民全体がその法律、権利、自由を正統にして合法的な政府のもとで享受できることを確かにする」ためにオレンジ公ウィリアム3世は命を擲って戦ったのである。
国際法や近代哲学が生み出され、数学や物理学、臨床医学等に著しい進歩がもたらされた17世紀オランダの文明は輝かしいものであった。その輝かしい文明が「世界史の奇跡」とまで賞揚されるのは、生み出された知識や技術のレベルが高いばかりでなく、それを支える底流として「信仰の自由」と「政治的自由」という二つの基軸が確立されていたからに他ならない。専制が罷り通っていた17世紀ヨーロッパにおいて、そのように底の深い文明であったが故に「世界史の奇跡」とまで称賛されているのであり、戦後日本の高度経済成長などという話とは全く次元を異にする話である。因みに絶対王政の権化ルイ14世の日常はどのようであったのか。起床の式、お祈り、拝謁、小食膳、大食膳、散歩、就寝の式、そして太陽王排便の際にはそれぞれ廷臣が参列し、その資格は厳重に決められていたという。1715年大王ルイの死に対して、フランスの衆民は「待望久しかった解放を神に感謝し」、王の葬列を口汚く罵り、酒を飲んで歌い、踊ってその死を喜んだという。ルイの「大御代(グラン・シェクル)」末期のフランスという国の国情を「荒れすさみ、たくわえがなくなった広大な病院」に例える者があった。その死から70年余り後になってルイの子孫はギロチンで首を切り落され、ジャコバン党とかジロンド党等々がギロチンその他を用いて反対派を殺しまくる日々が何年も続いたことは周知である。
ルイ14世が死去して2年後(1717年)のフランス宮廷を訪問したロシアのピョートル大帝は、かつての大宰相リシュリューの彫像を抱擁して「偉人よ、私はあなたにロシア帝国の半分をさしあげてもよい、残りの半分をいかに治めればよいかを教えて頂ければ。」と言ったという。20年前アムステルダムで「船大工」としての修業をしながら、身をもって西洋(西欧)を学び、ロシアの近代化を企図した大帝ピョートルの偉業(努力)の反面は彼の大好きな拷問や処刑に支えられた一種の茶番劇であった。前述のように(シリーズ11)訪欧直前の貴族会議でピョートルの西欧訪問計画に対しておずおずと反対した貴族や高位聖職者たちの心底にあったのは「ロシアでは国外に出ることは禁じられている。ほかの国民の風俗や考えを知ることにより、人々が隷属の鎖を断ち切ろうとすることが恐ろしいからである」という心情であった。これを一言で言えば「既成秩序の破綻に対する恐怖」ということになろう。リシュリューの像を抱擁したピョートルが好きでたまらなかった拷問や処刑は、文化の素質の低い当時のロシア衆民を統治するためには、必要な道具(政治装置)でもあった。シリーズ11で説明したように、ロシアも日本もその欧化の実態は表面的、外形的なものに過ぎず、西洋の文明をただ外面的に把握するという体質と姿勢は21世紀の今日まで連綿として温存されている。そしてこれは当然予期されたことではあるが、最近の新聞報道によれば、2005年5月9日、モスクワに世界53ヶ国首脳を招いて挙行された対ドイツ戦勝60周年記念式典に備え、モスクワ市幹部は、この連休は郊外で過すよう市民に勧め、モスクワ市警本部長は「精神の不安定な人々の首都立ち入りを制限する指令」が出されたことを明らかにしたという。壮麗なクレムリン宮殿に君臨するプーチン大統領が統治する現今のロシア社会の底流をなしているものは、実はピョートルや女帝エカテリーナの時代と大して変わってはいない。名著『ロシア人』の著者ヘドリック・スミスがいみじくも指摘するように、「ビザンツ帝国(東ローマ帝国)の遺産」と「ギリシャ正教(東方正教会)の伝統」という二大要素を底流として「専制」や「強権」はあっても「民主主義」あるいは「自由民権」などは、どこにも見当らないのがロシアという国の今日の実態である。片や日本国(民)の現状については本シリーズ11で述べた通りである。ピョートルの壮大な企図から160年余りも遅れてオランダへ留学生を派遣した徳川幕府は、留学生全員に国風の厳守を命じていた。榎本武揚ら留学生たちはチョンマゲなどをつけたまま、毎日どのような思いで学問を続けていたのであろうか。国風の厳守を命じた幕閣の心底にあったものはピョートルの西欧訪問計画におずおずと反対したロシア貴族達の心底にあったものと同じである。ウィリアム3世が命を捨てて護ったもの、「自由(Liberty)」という言葉にこめられた意味は限りなく広く、そして限りなく深い。ロシアも日本も国民の大多数は、この言葉と正面から向きあうことなく今日まで推移してきた。そのロシアも日本も間もなく少子高齢、前代未聞の人口減少国家に転落する。そこでの最大の問題は「国民の国家に対する貢献と、国家の国民に対する恩恵」の問題であり、古めかしい言葉で集約的に言えば「分配の問題」ということになろうか。そのような事態に対して日露両国民の大多数は「近代市民社会の市民」としての自覚(政治意識)を到底持ち合わせてはいない。一方、一旦手に入れた生活水準を引き下げることは、なかなか出来ないのが人の世の常である。そう遠くない将来、両国民は治安問題(手に入らないものを奪うという短絡的行動の激増)を含めて試練の時を迎えるであろう。 |
 |
 |
ケンブリッジ大学セント ジョンズカレッジ
校舎背面とケム川
(2004/12撮影)
第1校舎はマーガレット・ボーフォートの死後その遺志と基金によって1511年創立と当時に建設された。第2校舎は16世紀後半、第3校舎は17世紀に、ケム川の向い側の新校舎は1831年に完成した。 |
 |
|
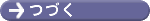
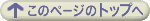 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |