 |
 |
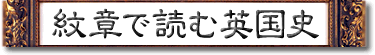 |
| 丸屋 武士(著) |
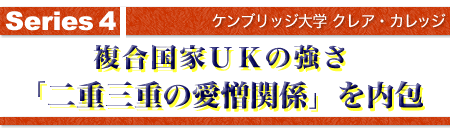 |
 1 2 3 4 1 2 3 4 |
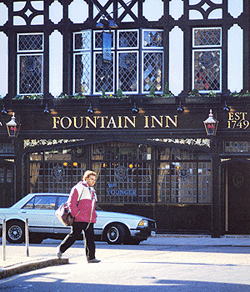 |
| ケンブリッジの街角 |
| (1985/11 撮影) |
| つまりそれほど、イングランドに対するスコットランド、ウェールズあるいはアイルランドの民族感情は根強く、かつ激しい。薩長に対する会津藩、南部藩のような関係を何世紀も続けてきたのがこれらの地域であり、しかも陸続きであるとはいえ、アングロサクソン系のイングランドに対して、スコットランドやウェールズはケルト系という、人種的(したがって言語的)にも異なった地域なのである。ちなみに、会津(福島県)の人々が135年前の戊辰戦争によって薩長から受けた仕打ちに対して21世紀の今日においてもどのような思いを抱いているのか、その好例をここに紹介したい。福島県議会議員(現在4期目)渡辺篤氏のホームページ表紙の一文をそのまま紹介します。 |
| 明治戊辰戦争で会津は「薩摩・長州」のスケープゴートにされた。会津藩は戦争をのぞまなかった。新政府に対して恭順の意を表したのに許されなかった。私は長州を許すことができない。戊辰戦争では武士だけでなく婦女子まで西軍によって虐殺された。そして斗南藩での出来事、明治、大正、昭和の初期まで賊軍として会津が痛めつけられたこと、明治戊辰後の藩閥政治が行われたことを忘れることはできない。会津の多くの人は良識人となり、大人になって過去のあつれきを指摘するのはどうかという意見が多くなっているが、私はあくまで明治戊辰戦争を批判していきたい。 |
|
|
| 近頃、日本人もテレビ観戦するようになった5カ国(イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、フランス)対抗ラグビー試合に対する、それぞれの地域の人々の熱狂の裏には、このような複雑な民族感情が働いていることを理解すべきである。エドワード1世(在位1271〜1307)あるいは更にさかのぼって「偉大なる名君」ヘンリー2世(在位1154〜89)の時代からの「文化交流の歴史」と、「二重三重の愛憎関係」を浮き彫りにする「5カ国対抗ラグビー戦」こそは、まさに国際試合の名にふさわしいインターナショナルなものである。早春のトゥイッケナムその他のラグビー場に響く歓声や怒声、罵声には数百年の間の歴史に記された数々の戦場における歓声や怒声、罵声と同じ思いがこめられていることを知らなくてはなるまい。 |
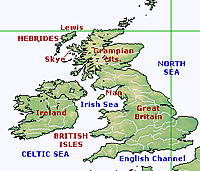 イングランド、ウェールズ、スコットランド、(北)アイルランド(英国の正式国名がUnited Kingdom of Great Britain and Northern Irelandであることを知っている日本人は案外少ない)が、「二重三重の愛憎関係」を内包しながら、太陽王ルイ14世のフランス、ナポレオンのフランス、ヒトラーのドイツとの戦いに勝ち、ヨーロッパ大陸からの支配を受けずに今日まで来たことは世界の奇跡である。 イングランド、ウェールズ、スコットランド、(北)アイルランド(英国の正式国名がUnited Kingdom of Great Britain and Northern Irelandであることを知っている日本人は案外少ない)が、「二重三重の愛憎関係」を内包しながら、太陽王ルイ14世のフランス、ナポレオンのフランス、ヒトラーのドイツとの戦いに勝ち、ヨーロッパ大陸からの支配を受けずに今日まで来たことは世界の奇跡である。 |
| その著『文明論之概略』において福沢諭吉は白人を評して「……争ふに勇あり、闘ふに力あり、智弁勇力を兼備したる一種法外の華士族と云ふも可なり。」と言った。その代表が英米人ということになろうか。21世紀の今日においてなお、世界中からの留学希望者がアメリカ合衆国に次いで多いのも、当然のことであろう。 |
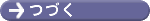 |
 1 2 3 4 1 2 3 4 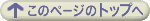 |