 |
 |
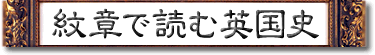 |
| 丸屋 武士(著) |
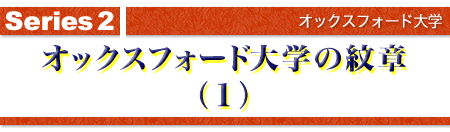 |
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 |
 |
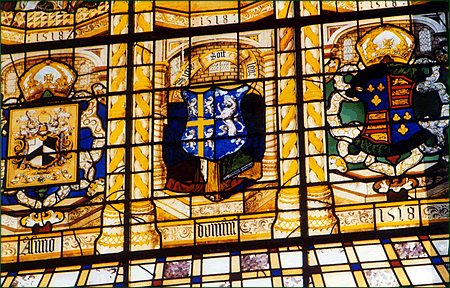 |
| (1985/11 撮影) |
| イギリスで最も偉大な天文学者であり、当時の科学者としてニュートンに次ぐ人物であるとされているエドモンド・ハレー (Edmond Halley) は1673年、オックスフォード大学クイーンズ カレッジに入学した。3年後ハレーは学位を取得せず、オックスフォードを去りセント・ヘレナ島へ観測旅行に出かけたが、後年オックスフォードの「サビル講座」担任の幾何学教授に任命され、65歳になって第2代グリニッジ天文台長に就任した。 |
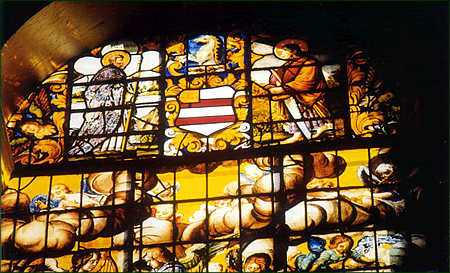 |
 |
 |
| (1985/11 撮影) |
| 1684年(日本ではこの3年後5代将軍綱吉の生類憐みの令が発せられた)8月、28歳のハレーは初めてケンブリッジ大学トゥリニティー カレッジ(現皇太子チャールズはここの卒業生である)に12歳年上のアイザック・ニュートンを訪ねた。2人はすっかり親しくなり、その独特のひかえめな性格から自分の開発した理論や実験結果を公表したがらないニュートンにかわって2年後にはハレー自身の費用でニュートンの革命的大作『プリンケピア(自然哲学の数学的原理)』を出版した。1703年名誉ある王立協会会長に選任されたニュートンは引力が地球と物体との間ばかりでなく、星と星との間にも働いていると考え、惑星や彗星の運動がこれによって計算できることを実証した。ニュートン力学を駆使し、計算機もコンピューターもないあの時代に甚大な労力を費し、24個の彗星の軌道を計算したハレーは1531年、1607年、1682年に観測された彗星が、実は76年の周期を持つ同一の彗星であることを発見、次の彗星は1758年に出現することを予言した。1742年ハレーは84歳で没したが、彼の死後その予言通りに現れた彗星はハレー彗星と命名された。このハレー彗星は、1986年にも世界中の人々の注目のうちに登場し、多くの愛好家たちに観測された。 |
 |
| (1985/11 撮影) |
| 1531年この星を観測したドイツの天文学者アピアヌスは、彗星の尾が常に太陽と逆の方向に向いているという天文学史に残る大発見をした。 |
 |
 |
 |
| (1985/11 撮影) |
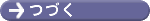 |
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 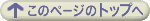 |