 |
 |
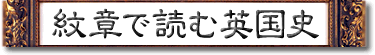 |
| 丸屋 武士(著) |
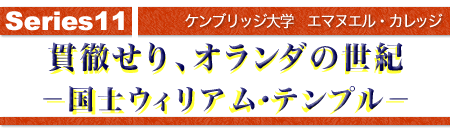 |
 |
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 |
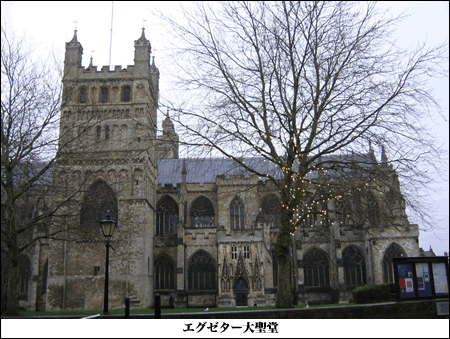
1688年11月9日堂々と進軍して来るウィリアム軍を見ようと、近隣の村々から住民がくり出して沿道を埋め、エグゼター大聖堂においては感謝(無事上陸を祝ってか?)の礼拝が執り行われた。関が原の合戦においてさえ洞ヶ峠を決め込む者がいたように、直ちにウィリアムの下に馳せ参ずる有力者はいなかった。ここエグゼターを拠点におよそ10日間、ウィリアムはオランダから持ち込んだ印刷機も使って次々と書簡や声明を発表し、プロパガンダ攻勢をかけた。11月17日、イングランド西部の実力者エドワード・シーモアがエクゼターに現れたのをきっかけに有力者が集まり始めたが、ウィリアムは「招かれてやって来たというのに、もう少し早いと思っていたよ」と表面上はうれしそうな顔を見せず、つっけんどんな応対をしたという。幼い頃から隠忍自重を重ね、艱難辛苦を乗り越えて来たウィリアムらしい冷徹な演技であった。 |
|
|
1688年(元禄元年)11月、6万部も印刷されたウィリアム3世のイギリス臣民に発した宣言の「あらゆる人々を信条を理由とした迫害から守ること、そして国民全体がその法律、権利、自由を正統にして合法的な政府のもとで享受できることを確かにする以外の何物でもないのである・・・・・」等々の文言を読んでも聞いても、これが発布されてから180年も後の明治維新の頃に理解できた日本人は何人いたであろうか。我々は今日に至ってもこのような言葉を理解する「生活感覚」あるいは「皮膚感覚」を持っているようには思えない。
大帝ピョートルがオランダやイギリスで体で学んだ西欧を基に50年後女帝エカテリーナの時代のロシアは露土戦争によってトルコを打ち破り、プロシャのフリードリッヒ2世やオーストリアのヨーゼフ2世(マリー・アントワネット兄)と謀ってポーランドを分割する等、ロシアの国勢は大いに伸張した。ところがこの時代のロシアを見聞したフランス人シュバリエ・ド・コルブロンは、思想の進歩を標榜するロシア人たちが、本当のヨーロッパ文明には全く無知であり、ロシアの文化的外観の背後にあるギリシャ正教という信仰生活の古来からの形式や、族長的な厳しいモラル等々のロシアの伝統が、本質的な変化をとげるに至っていないことを見抜いていた。(アンリ・トロワイヤ著『女帝エカテリーナ』中央公論社刊、1980年)
ロシア社会を観察する時、見逃してならない主要な要素はビザンツ帝国の遺産と東方正教会(ギリシャ正教)の伝統であり、このことはプーチン大統領が支配する今日のロシアにおいても変わりはない。名著『ロシア人』(時事通信社刊、1978年)の著者ヘドリック・スミスが(とりわけその下巻において)鋭く指摘しているように、我々の多くはロシアの本質的な部分についての視点に欠けているようである。
|
  |
 |
| 西欧訪問に先立って、ピョートルはロシア貴族50人に国外退去を命じ、家族と離れて従者1人と共に、イタリア人、イギリス人、オランダ人のところに住み込んで、ロシアがヨーロッパ一の強国となるために、必要なことすべてを学んで来ることを命令した。その直後の1696年12月6日、ピョートルが貴族会議で自らの西欧訪問計画を発表した時、貴族や聖職者は偉大なる君主が、自らの治めるべき国家とロシア正教会の輝きから遠ざかり、カトリックとプロテスタントの国を漫遊することが許されて良いわけがなく、そもそも外国のパンを食らうことが、もう堕落ではないかとおずおずと諫めたという。しかしながら、はっきり言えば、反対する貴族や聖職者の心底にあったのは「ロシアでは国外に出ることは禁じられている。ほかの国民の風俗や考えを知ることにより、人々が隷属の鎖を断ち切ろうとすることが恐ろしいからである」という心情であり、ロシアのこの時代から150年以上後に「攘夷絶交」とか「好和開交」とか議論していたどこかの国の人々の心情とピッタリ一致する心情ではないか。余談になるが訪欧の3年前、1694年7月、ピョートルがアムステルダムに注文した軍艦「聖なる予言者」号がついに44門の大砲と40人の水夫とを載せてアルハンゲリスク港に到着した。町には祝砲が轟き、鐘が鳴り、22歳の皇帝ピョートルは踊り出さんばかりに喜んで、この軍艦の船尾に着ける旗をオランダと同じ赤、白、青の横縞で、ただ順序を入れかえたものに決めたのである。 |
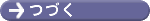 |
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 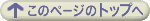 |