 |
 |
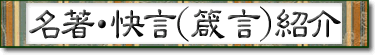 |
| 丸屋 武士(選) |
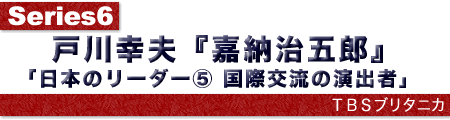 |
| (2003年1月) |
| ソニーやホンダが日本のメーカーであることは世界中で知られています。しかしながら日本の首相の名前を知っている人は西洋(世界)には殆どいないと言って過言ではありません。ところが世界中で柔道の試合が行われる時、「ハジメ」「マテ」「イッポン」「ワザアリ」「コウカ」等々の日本語がサッカーの「オフサイド」ラグビーの「ノッコン」等々と同じく世界語になっているのです。 |
|
|
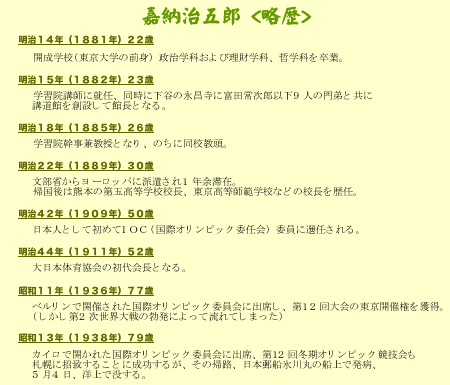 |
| 学習院教授となった頃(26歳)の治五郎の柔術研究と練習は激烈を極め、元旦から大晦日まで1日も休まず午後3、4時から夜中の12時過ぎまで稽古を続けた。治五郎本人が一人でも多くの弟子を相手にほとんど休む間もなく、また門人たちにも稽古中はながく休むことを許さなかったという。 |
|
|
| ・・・治五郎はこう語っている。「私はかってからだも弱く、非常な癇癪もちですぐにカッとなる性質であったが、柔術をやりはじめて、からだがじょうぶになるにつれ精神も落ち着いてきて自制力がいちじるしく強くなったことに気づいた。と同時に柔術の勝負の理屈が社会の他のことがらに応用できるものであること、また勝負の練習に付随する知的練習はなにごとにも応用しうる一種の貴重な練習であることを感ずるようになった。とはいっても従来の柔術や練習方法がそのままでよいとは思わなかった。だから相当のくふうを加えれば、たんなる武術としてだけではなく、知、徳、体の養成にまことに貴重な効果をあげうるにちがいない。今日の青年にもっとも必要なものは道徳であるから、これを柔術によって教える。つまり心と身の鍛錬の法としたい。さすればこの時世のなかでも柔術は受け入れられ、十分に伸びていける。 |
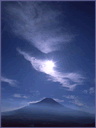 |
| そもそも柔(やわら)とは力と力とを闘かわせ、技によって勝敗を決するものだから術というのがほんとうかもしれない。しかし自分はこれをたんに技の優劣だけでなく心を修行する法にまでもち込みたいと考えた。なぜ相手に負け、なぜ相手に勝つことができたかを追求してその原理を発見し、原理よりして術に及ぼし、その原理の道を人生に生かしたいと願ったのである。すなわち柔(やわら)とは相手の力に抵抗せず、衝突の力を避け、敵の力の乗ずべきに乗じてこれを倒す術である。これを心の作用に応用するときは、たとえば人と対論するのに相手が興奮し、いきり立ち、口角泡をとばして食ってかかってきた場合、こちらは静かにこれに対し、諄々−じゅんじゅん−として道理を説けば、ついには相手を納得させ、説得できるというもので、これは勝利である。 |
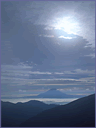 |
| そこで私は従来の柔術という名称を避け、私がやるのは柔道であると命名した」 |
|
| 戸川幸夫『嘉納治五郎』より(TBSブリタニカ) |
ロシアのプーチン大統領は、森の中の自宅の一室にブロンズ製の嘉納治五郎座像(高さ80センチくらい)を安置している。
生来すぐカッとなる性分のプーチンは柔道を学んだことによって自分の人生が変わった(決まった)と明言している。 |
|
|
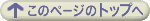 |