 |
 |
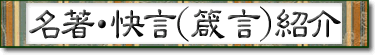 |
| 丸屋 武士(選) |
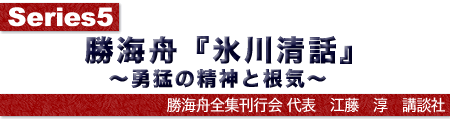 |
| (2003年1月) |
| なにしろ人間は、肉体が壮健でなくてはいけない。精神の勇ましいのと、根気の強いのとは天下の仕事をする上にどうしてもなくてはならないものだ。そして身体が弱ければ、この精神とこの根気とを有することが出来ない。つまりこの二つのものは大丈夫の身体でなければ宿らない。ところが日本人は、五十になるともうじきに隠居だとか何だとか言って、世の中を逃げ去る考えを起こすが、どうもあれでは仕方がないではないか。しかし島国の人間は、どこでも同じことで、とにかくその日のことよりほかは、目が付かなくなって、五年十年の先はまるで黒暗−くらやみ−同様だ。それも畢境、局量が狭くって、思量に余裕がないからのことだよ。もしこの余裕といふものさえあったなら、たとえ五十になっても、六十になっても、まだなかなか血気の若武者であるから、この面白い世の中を逃げるなどというやうな、途方もない考えなどは決して出ないものだ。 |
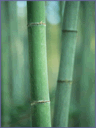 |
| それであるから、昔の武士は、身体を鍛えることには、よほど骨を折ったものだよ。弓馬槍剣、さては柔術などといって、いろいろの武芸を修行して鍛へたものだから、そこでおれのやうに年は取っても身体が哀へず、精神も根気もなかなか今の人たちの及ぶところではないのだ。 |
 |
| もっとも昔の武士は、こんなに体を鍛へることには、ずいぶん骨を折ったが、しかし学問はその割にはしなかったよ。それだから、今の人のやうに、小理屈をいうものは居なかったけれども、その代り、一旦国家に緩急−かんきゅう−がある時は、命を君の御馬前に捧げることなどは平生ちゃんと承知して居たよ。いはゆる君辱められるば、臣死するといふ教へが、深く頭の中にし染み込んで居たから、いざという場合になると、雪のやうなる双肌−もろはだ−を押しぬいで、腹一文字に掻き切ることを何とも思はなかったのだ。しかるに、学問に凝り塊まって居る今の人は、声ばかりは無暗に大きくて、胆玉の小さきことは実の豆のごとしで、空威張には威張るけれども、まさかの場合に役にたつものは殆んど稀だ。みんな縮み込んでしまふ先生ばかりだよ。 |
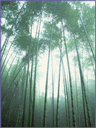 |
勝海舟『氷川清話』より(勝海舟全集刊行会 代表 江藤 淳)
(講談社) |
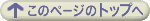 |