 |
 |
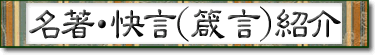 |
| 丸屋 武士(選) |
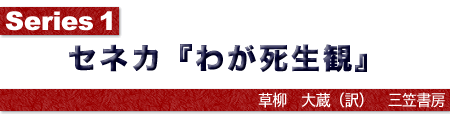 |
| (2003年1月) |
| さらに、私たちはちょいちょい自分の殻に閉じこもる必要がある。それは、性格が違う人々と交わると心の平静が乱され、感情が刺激され、まだ十分にいやされていない心の痛みがさらに悪化するからである。 |
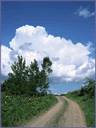 |
| とは言っても、孤独な生活と多数の中の生活とは結び合わされ、交互に割り振られることが望ましい。孤独に住めば人恋しくなり、多人数の中に住めば一人になりたくなり、孤独な生活と群集の中の生活とは相互にいやし合う。孤独になれば人の世の中に住む煩わしさがいやされ、人々の中に住めば独り住まいの退屈がいやされる。 |
 |
| また、同じ種類のストレスに心をさらし続けてはならない。娯楽で心を転換しなければならない。ソクラテスは恥ずかしがらずに幼児たちと遊んだし、カトーは国事に飽きるとワインを飲んでくつろいだ。心にはくつろぎが必要である。休養をとると心はよみがえり、生き生きとなる。 |
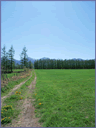 |
| 豊な畑地も休耕しないで多作すれば、地力はたちまち消耗してしまう。同様に動きづめでは気力が衰える。心を少しの間解放してくつろがせれば、その活力は回復する。精神を酷使し続ければ倦怠感と無気力が生れてくる。しかし、スポーツも娯楽も濫用すると心の活力がかえって失われる。例えば、元気を回復するためには睡眠も必要であるが、昼も夜ものべつ眠ると死んだようになってしまう。だらだらするのと、心の束縛を取除くこととは大違いである。 |
 |
| 立法院は、幾日かの祭日を設けて国民にお祭り騒ぎを押しつけているように見えるが、実は、国民の仕事を時折中断して日々の労苦を軽減する事が必要であるとの趣旨からである。毎月、一定の日数を休日と定めた偉人もいるし、一日を仕事の時間と遊びの時間に分けた偉人もいた。大雄弁家のアシニアス・ポーリオは、確かこのような規則を守っていて、十時以降はたとえどんな仕事でも決してしなかったということである。彼は十時過ぎると手紙さえ読まなかった。読めば何か新しい事が起こって緊張を強いられるかもしれないからであって、日没までの二時間は一日の疲れをいやすために別にしていたのである。 |
 |
| セネカ『わが死生観』より(訳:草柳大蔵)(三笠書房) |
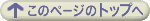 |