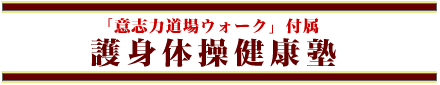| − DVD付属小冊子『緒言』より − |
 |
| 「意志力道場ウォーク」付属「護身体操健康塾」は日本固有の文化である「古流柔術」を土台として、「敏捷な体さばき(運足)」と「合理的な手さばき(手刀)」とを老若男女全ての人々が習得(体得)できるよう考案、構成された「丸屋武士の護身体操」を普及奨励する一種の学習塾であります。DVDを見ながら、教室(塾)の中でリーダーの動きを見て共に運動する感じになるよう工夫された独自の運動システムです。 |
| 幕末、佐久間象山、吉田松陰、勝海舟や渋沢栄一らが探求した「陽明学」においては「知行合一」という思想が根底にありました。よく考えてそれを実行にうつし、単なる「知」と「行」が「真知」と「真行」に発展するという「くりかえし」の効用、すなわち「行」の教育の効用が説かれました。当システムはこの考えに沿って展開され、「体さばき」と「手刀」とを習得(体得)するために一定時間(一定期間)、基本動作、応用動作のくりかえし練習を「行」として一人で実行できるところに特徴があります。ソロバン塾に入門しても何ヶ月、あるいは何年も続けなければ珠算が上達しないのと全く同じで、絵(写真)や映像をいくら眺めても武道が身に付くことはありません。珠算において指が無意識に動くようになるのと同じく、反復練習によってからだが無意識に動くところまでもっていくのが当塾の狙いです。何事においても安易、安直な風潮が蔓延している昨今の世の中ではありますが、「時間をかけ、汗をかかなければ」真に「身に付く」ものはありません。では何故「体さばき」と「手刀」の二つを基軸としたのか、その理由をお話しましょう。よく言われるように鎌倉時代から伝来の鎧組打ちを主体とする日本の格闘技術は、鉄砲伝来さらには戦国の世に終止符が打たれた徳川時代に至って大きな変遷を遂げることになりました。天下泰平、平服組打ちの世となって、鎧を身につけずに相手の打・突・蹴あるいは斬突を防ぐことを目的とする格闘技術が広く深く追求される時代になったのです。今日、古流柔術として知られる独自の格闘形態と「わざ」を発展させた柔術流派は幕末において179流もあったとされています。どの流派においても、その目的とするところは不時の外敵から自分を護るための護身術でありました。そして最も示唆的かつ重要なことは無限定(ルールなし)の各種各様のこれら格闘技術の核心が、「敏捷な体さばき(運足)」と「合理的な手さばき(手刀)」の二点にあったことであります。ここに着眼して立案、構成され、一人でも練習、鍛錬できるシステムが当「護身体操健康塾」です。これを要するに、当塾の基本目的は「体さばき」と「手刀」を習得(体得)し、物理的(身体的)衝突に対応する基本動作を身につけることであります。同時にこのシステムに沿った運動を一定期間継続することによって「心身の健康を保持増進する」という、より大きな目的が達成されることを狙うものであります。気合をこめて手と足を同時に働かせる運動としての効用は、開始間もなく汗ばんでくるように、メタボリックシンドローム解消の一助にもなろうかと思います。ここに「心身の健康」、と敢えて「心」の字を加えたのは筆者のささやかな願いがあってのことであります。本来、生死の岐路に立って殺傷を目的とする武術とりわけ剣術においては特に江戸時代に至って、相手を殺傷することよりも剣術の修練に伴う精神的な意義、内面的人間性が深く探求されるようになりました。死生の場における心構え、態度そして攻防の技術の探求がしだいに醇化され、人間の修養の道として発展し、敵を意識するよりは己の心の敵すなわち自らの内面的葛藤(恐怖や怒り等々)を克服する道が探求されました。優れた剣術家たちによる儒教、仏教(特に禅宗)、神道あるいは老荘の思想をも包含する「わざ」から「みち」への探求によって日本武道に独特の文化的価値が付与されたのです。今、この貴重な先人の遺産が現代日本の混迷を脱する一助になることを切に願うものであります。 |
| ところで、社会のIT化が益々推進されるなかで「知」の教育もまた強力に推進されねばなりません。しかしながら、知識欲は常に外への広がり、新奇を求めて留まるところを知らず、ついには「心の平衡」を失うところまで往きかねません。昨今、諸々の要因によって「心の問題」を抱える人々は増えこそすれ減ることはないようです。(日本)陽明学の始祖中江藤樹は「文の徳は仁、武の徳は義」であり、儒者といえども文武の兼備が必要と論じ、その弟子熊沢蕃山は、武芸も「精神義に入る時は大道に通ず」と言い、武芸修練の大切なことを力説したとされています。言うまでも無く鍛錬主義が全ての問題を解決する道ではありません。しかしながら冒頭お話した「行」の教育の重要性は増すばかりではないでしょうか。 |
2007年7月
「護身体操健康塾」
塾長 丸屋武士 |
 |
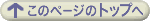 |