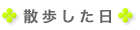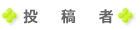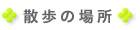(中)
話を「フィリピン訪問団一行」に戻すと、明治38年7月26日午前に行われた明治天皇との謁見に続いて、皇族の重鎮・伏見宮その他皇族主催の歓迎午餐会が開かれ、伊藤博文枢密院議長以下各元老、桂太郎首相以下各大臣、宮内官、外交官、武官が陪食し、その後タフトら一同は吹上御苑を観賞する。
引き続き夜には、外務大臣(渡米した小村外相に代わり外相を兼任する桂首相)が主催する晩餐会が催された。
歓迎行事は引きも切らず、翌7月27日、芝の「紅葉館」において、京浜間実業家主催の「米国貴賓招待会」が開催され、タフトやアリスに率いられた一行に対して、3年前の訪米(前述した明治35年の米欧漫遊)の折、現地新聞に「東洋のJ・Pモルガン」と紹介された渋沢栄一が、実業家総代として歓迎の辞を述べたのである。
因みに「紅葉館」は、現在東京タワーが建っているあたり(芝区芝公園20号地)の4600坪の敷地(通称紅葉山)に建てられ、300名限定会員制の純和風高級料亭として、外国人接待の場、政治家、実業家、文人、華族、軍人の社交の場として、広く知られる東京名所のひとつであったが、昭和20年3月の東京大空襲で焼失した。
顧みると明治11年3月12日に認可された東京商法会議所は、38歳の渋沢栄一を初代会頭として明治24年7月には東京商業会議所に、そして昭和3年1月には東京商工会議所と名称の変更は行われたが、明治11年から明治38年4月まで27年間、初代会頭を務めた渋沢栄一は日本を代表し、比肩する者が無い「世界的実業家」であった。
明治12年7月3日、大統領職を終えて世界旅行中のアメリカ合衆国前大統領グラント将軍の来日に際しては、渋沢(39歳)は東京接待委員総代として新橋駅にグラント夫妻を迎え、その後数々の歓迎行事にも出席、8月5日には東京接待委員長として、浜離宮を宿舎としていた大統領夫妻を王子飛鳥山の自邸に招いて午餐会を開催した。
その際、明治10年に発足したばかりの東京大学に文学部第2期生(同期6名)として在学中の嘉納治五郎は渋沢の求めに応じてか、同じく東大在学中の五代竜作(豪商・五代友厚の養子、後に東大工学部教授を辞して養父の事業を継ぐ)と共に、グラント夫妻の前で柔術(天神真楊流)の「乱取り」を披露したという。
柔術から止揚(アウフヘーベン)した「講道館柔道」は、日本発(初)世界標準として益々充実発展し講道館への入門者は引きも切らず、明治42年5月3日、嘉納治五郎はそれまでの個人経営の講道館を法人化したが、その理事には若槻礼次郎(大蔵次官、後に首相)と矢作栄蔵が、そして監事として柿沼谷蔵と渋沢栄一が就任している。
さて特筆すべきは、上述した明治38年7月27日、実業家総代・渋沢が祝辞を述べた京浜間実業家主催の「米国貴賓招待会」が行われた日の早朝、日露両国及び日米両国にとって決定的な会談が極秘で行われたことである。
そもそもタフト陸軍長官一行「アメリカ合衆国フィリピン訪問団」の目的は、明治31年に戦われた「米西戦争」によって、スペインからアメリカ合衆国にその支配権が移ったフィリピンの視察であり、横浜(日本)にはその途中で立ち寄った「かたち」ではあった。
だが、「人類愛と文明(humanity and civilization) の為の平和回復」という大義名分だけでは戦争を終わらせることは出来ない。
「打算と不条理の横行」が国際社会(人間世界)の一面であるとすれば、明治38年7月27日午前、「フィリピン訪問団」一行の宿舎である芝離宮において、通訳としての珍田捨巳外務次官を伴った桂太郎首相とタフト陸軍長官の会談こそは、正に日米双方がお互いのハラ(打算)を確認し合うものであった。
「桂タフト協定」と呼ばれる協定は、この日の桂太郎とウィリアム・タフト両者の会話を記録した「覚書」であり、日本側のその原文は焼失したとかで存在しない。
しかしながら、同じ頃(明治38年8月12日)ロンドンにおいて調印された「第二回日英同盟協約」の第3条「日本と韓国の関係」と、第4条「イギリスとインドの関係」を読んで推し量れば、事の本質は一目瞭然である。
同協約の第3条をそのままにして、第4条のイギリスとインドの関係を「アメリカとフィリピンの関係」と把握して、「当たらずとも遠からず」ということではないか。
日本を離れフィリピンに向かったタフトは、桂首相との会談内容をエルヒュー・ルート国務長官に電信で送り、それは間も無くルーズベルト大統領にも到達した。
「東アジアの勢力均衡」という観点から日露の関係(戦争)を観て、開戦以来、「厳正中立」を装いながら、金子堅太郎とは2年簡に十数回、二人だけの会談を続けてきたルーズベルトは、日本が朝鮮半島における支配権の見返りに、フィリピンというアメリカにとってのアキレス腱を、未来永劫狙わないことを確認したことは大きな安心材料となり、タフトの電文によって日露講和会議に臨むハラを固めたようである。
巨漢タフトは体重160キロの偉丈夫であり、ルーズベルトの次にアメリカ合衆国第27代大統領に当選したが、その体重によってホワイトハウスのバスタブを壊してしまったと言われている。
余談ながら、明治43年4月14日、アメリカ大リーグ(MLB)の開幕日に、アメリカ史上初めて大統領として首都ワシントンの球場で「始球式」のボールを投げたのが、ウィリアム・タフトであり、以後ジミー・カーター、トランプそして現大統領バイデンの3人を除いて歴代大統領は、このしきたりを踏襲してきた。
そういう記念すべきイベントを創始したタフトであったが、翌々明治45年4月14日(大リーグ開幕の5日前)発生した20世紀最大の海難事故となった「タイタニック号沈没」によって、この年の始球式出席は断念した。
オハイオ州シンシナチ―の名家の出であるタフトは、明治34年から37年までマニラにあってフィリピンの初代民政長官を務めたが、フィリピン人に対する人種的偏見を持たず、公正に振る舞ったばかりでなく、行政官として優れた才能を遺憾なく発揮したと言われている。
明治31年の「米西戦争」によって老大国スペインからキューバとフィリピンの支配権を奪ったアメリカ合衆国であったが、翌明治32(1899)年、今度は完全独立を目指すフィリピン人を相手に「米比戦争」を戦う羽目に陥る。
前年の「米西戦争」でアメリカ陸軍第一師団第二旅団長としてマニラを占領したアーサー・マッカーサー(ダグラス・マッカーサー元帥の父親)が北ルソン方面のアメリカ軍司令官となり、翌明治33年、マッカーサー准将はフィリピン派遣軍指令官兼フィリピン軍事総督に任命される。
アメリカ人にとっては後のヴェトナム戦争と同じく、思い出したくもないことではあるが、フィリピンのジャングルにおけるゲリラ戦の代償は高く、アメリカ兵の戦死者は4200名、負傷者は2800名に上った。
マッカーサー軍事総督が悪戦苦闘しているフィリピンに明治34(1901)年、初代民政長官として赴任したタフトは、毎日朝から事毎にマッカーサーと衝突し、結局マッカーサーが本国に召喚されることになって両者の喧嘩はケリがついた。(後の世のダグラス・マッカーサー元帥とハリー・トルーマン大統領の対立と同じ構図?)
性格的にも政策的にも全く相容れない二人であったが、皮肉なことにその後タフトは、セオドア・ルーズベルト大統領の下で陸軍長官(Secretary of War)に任命され、更にはルーズベルトの次の第27代大統領となってマッカーサーの上司となる。
不本意にもフィリピンを去ってアメリカに帰ったアーサー・マッカーサー陸軍少将は、満州に於ける大規模な戦闘(奉天大会戦)は既に終わってしまった明治38年3月、日露戦争観戦武官として東京に赴任する。
タフト率いる「フィリピン訪問団」を送迎するという、つらい(?)役回りを終えた直後の明治38年8月、アーサー・マッカーサー少将はアメリカ公使館付武官となり引き続き東京に滞在したが、息子(次男)のダグラス・マッカーサー陸軍中尉を自らの副官として呼び寄せ、明治38年10月29日ダグラス・マッカーサーは横浜に上陸した。
3日後の11月1日、息子のダグラスと共にマッカーサー少将夫妻は横浜から長崎まで西下、長崎から8か月に亘るアジア情勢視察の旅に出る。
後の連合軍(日本占領軍)総司令官ダグラス・マッカーサー元帥は、25歳の時、日本の土を踏み短時間ながら日本を見て帰ったこと、そして父アーサー・マッカーサー少将はアメリカ公使館付武官として離日の前に、満州の野で勝利した日本陸軍の黒木第一軍司令官、奥第二軍司令官、乃木第三軍司令官らと東京で会見し、戦場における感染症(伝染病)予防等について意見交換の機会を持ったことも記憶しておきたい。
アメリカで 陸軍大将位が設けられたのは後の(第一次世界大戦時?)のことで、ア ーサーはその後、アメリカ陸軍最高位の陸軍中将に昇進したが、そのアリストクラティックな性格が災いしたか、アメリカ陸軍を束ねる陸軍参謀総長に任命されることはなかった。
一方、驚異的な成績(25年ぶり?)で陸軍士官学校を卒業したダグラス・マッカーサー中尉(26歳)は、8か月に亘りフィリピン、インド等々を両親と共に視察してアメリカに帰国した明治39年、ルーズベルト大統領に認められてか、ホワイトハウスにおいて軍事顧問補佐官を務めることになる。
本題に戻ると、前述したように渋沢栄一率いる「渡米実業団」一行はアメリカ各地を訪問、多くの有力者に面会したが、明治42年11月1日、首都ワシントンに到着した一行は、そこに三日間滞在し、その間にノックス国務長官やタフト大統領との面会(表敬訪問)が行われたのであった。
渋沢にとっては4年前の芝「紅葉館」における歓迎会で、京浜間実業家総代として祝辞を述べて以来、二度目となるタフトとの会見であったが、両者の胸中はどのようなものであったか。
前述したように、実業家総代・渋沢がタフト率いる「フィリピン訪問団」に祝辞を述べる午餐会があった4年前の明治38年7月27日の朝、芝離宮で行われたタフト陸軍長官と桂太郎首相のハラの相互確認が日露講和会議の運命を決めた最大の要因であったことを、タフトは当事者として分かっていたが、民間人・渋沢には桂・タフト極秘会談のことは伝わっていなかったのではないか。
ルーズベルト大統領は前述したように、芝離宮における会談についてのタフトからの電信を受けて、日露講和会議談判破裂の際は、その責任を全てロシア皇帝のせいにするハラを固めていた。
ポーツマス講和会議については吉村正氏の名作『ポーツマスの旗』に詳述されているが、同講和会議の結果を受けて「ノーベル平和賞」を授与されたセオドア・ルーズベルト大統領は、ノーベル賞授賞アメリカ人・第一号となった。
それは日本から西南にある国々が「東南アジア」とか呼ばれ、近東、中東、極東等の言葉が日常茶飯に使われ、「世界のことはヨーロッパで決められる」時代の終わりを告げる兆候でもあった。
現在アメリカ人のノーベル賞受賞者は、日本の12倍強、世界で断トツの380人余となっている。
「平和賞」の授与は、「化学賞」「物理学賞」等が授与されるスウェーデンではなくノルウェーで行われるが、それはノーベル賞の創設者アルフレッド・ノーベルが、「スウェーデン、ノルウェー両国の過去の確執(争い)を超えての和解と平和」を祈ってノルウェーで行うことにしたことを、認識する人は昨今少ないようである。
明治42(1909)年12月17日、「渡米実業団」一行は帰国し、前述したように、団長・渋沢栄一は各種数多の団体による帰国歓迎会に年を越えても招かれ、談話(米国旅行談)や講演に忙しかった。 (続く)
|
|