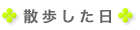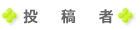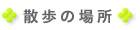Ⅱ-4 何礼之の恩師フルベッキの飛躍
さて、オランダはザイストに生まれ22歳の時アメリカに移住し、安政6(1859)年、29歳で来日して以来、フルベッキは殊更、長崎の自然の美しさを愛で、一緒に来日した宣教師シモンズやブラウンのいる横浜に比べて、長崎は冬の寒さも厳しくなく、治安も良く、漢字やオランダ語の知識がある日本語の教師も身近にいて、彼は手放しで長崎が気に入っていた。
なんといっても住民が外国人に慣れていて、仲良く交流できることを最も喜んでいたのである。
ところが、文久2年1月には「坂下門外の変」、4月には「寺田屋事件」、8月には「生麦事件」等、凄惨な殺傷事件が続発し、険悪な雰囲気や誇大な風説が長崎にも影響を及ぼし、2年前に長男が誕生したフルベッキ一家は、1863(文久3)年4月には出島のケンペル邸に引っ越し、5月には上海に避難を余儀なくされてしまった。
夏の上海の耐え難い灼熱、更には疫病等にも辟易していた一家は、10月13日、多少の危険は覚悟の上で長崎に戻り、とりあえず出島の高い家賃の借家に落ち着いた。
翌元冶元(1864)年2月27日、一家は出島を出て長崎市内の家賃の安い家に移ることができた。
フルベッキは隣近所の人々と気楽に付き合い、以前からの学生たちにも殆ど毎日会ってはいた。
ところが長崎市内には、前年5月、一家が上海へ逃れた頃に長州藩が外国船を砲撃したことに対する報復攻撃が近々行われるという噂がしきりであった。
噂は現実となり、この年(1864年)7月27日と28日の2日をかけて、横浜港に集結した四国連合艦隊(イギリス軍艦9隻、オランダ軍艦4隻、フランス軍艦3隻、アメリカ商船1隻)は、イギリス海軍クーパー中将を総司令官として、総員5000の兵力をもって下関海峡に向けて出港した。
8月5日始まった戦闘は8月7日には終結し、長州藩は「焦土作戦」などと、後の時代のどこかで聞いたような勇ましげなことを怒号していたのに、たった3日で止戦媾和という体たらくであった。
敵海兵隊の上陸をも許して、全ての砲台を破壊されてしまった長州藩は、この敗戦の後始末を脱藩の罪で野山獄に繋がれていた高杉晋作に委ね、井上聞多(馨)が通訳を務める。
挙句に、喧嘩を吹っ掛けたオトシマエとでもいうべきか、300万ドル(300万両?)という巨額の賠償金を請求され、到底その支払い能力のない長州藩の代わりに、徳川幕府がとりあえず半額の150万ドルを支払い、以後、分割払いで明治新政府が明治7年まで払い続けたのであった。
こういう目に合わされても頑迷固陋の攘夷派は、「西洋かぶれ」の井上馨や伊藤博文を切ってしまおうという雰囲気であったという。
そうではあっても大勢として、日本人に攘夷の不可能を思い知らせるために「文明国」の武力を示す必要を感じていたイギリス駐日公使オールコックの狙いは、十分に達成された。
この前年、薩英戦争に敗れた薩摩藩と競うように、長州藩の俊秀を選抜して欧米へ留学させるという流れが止まることはなく、禁制を破り、変名を用いて欧米に留学した人々が、帰国して日本近代化の核心となったからである。
余談になるが、四国連合艦隊が2日をかけてデモンストレーション(示威行動)を行い出港していった横浜港には、イギリス軍艦1隻、アメリカ軍艦1隻が待機し、陸上においてはイギリス陸軍第20連隊第2大隊を中心とする1300余りの兵力が、横浜租界居留民保護の任務に当っていた。
さて、この元冶元年(1864年)は、本編の主人公・何礼之にとっても、何礼之の恩師フルベッキにとっても、一大飛躍の年であった。
前述したように 、この年の初めに何礼之は長崎奉行の許可を得て、幕臣(長崎奉行支配定役格)として奉行所(貿易)事務に携わりつつ、官立「洋学所」学頭兼任のまま、自宅に「私塾」を開設することになったからである。
名前のない何の私塾に敢えて名前を付けるとすれば、「何礼之英学塾」とでも呼ぶべきか、フルベッキは何礼之の依頼によって、元治元年春から、その「私塾」で英語を教えるようになった。
その後、フルベッキの指導を受けた何礼之や平井義十郎らの目覚しい進歩に動かされたのか、元治元年6月16日、フルベッキは、長崎アメリカ領事ジョン・ウォルシュを介して長崎奉行・服部長門守から年俸千二百両という高給で長崎洋学所の教師就任を依頼された。
年俸千二百両(1200ドル)は、当時の知行2400石取りの武士の実収入に相当する額である。
フルベッキはその申し出を受託し、8月2日から「洋学所」で授業を始めたが、この年、「洋学所」は「語学所」と名称が変わり、英語、ロシア語、フランス語が教えられるようになっていた。
翌慶応元年(1865年)8月、「語学所」は大村町から新町にある旧長州藩蔵屋敷に移転し、その名称も「済美館(せいびかん)」と改められ、学頭・何礼之と平井義十郎の下に、英語、フランス語、ロシア語、ドイツ語、清国語という語学ばかりでなく、世界史、地理、理化学、天文、経済も教科として取り入れられ、英語の担任はフルベッキ、何礼之、柴田大介以下9名であった。
フルベッキは1週間のうち土曜、日曜以外は毎日出勤、午前9時から11時までの2時間、授業は全て英語で行われたため、上級者が対象であったという。
一方、何礼之の「私塾」におけるフルベッキの授業は、午後にでも行われたのであろうが、いずれにしてもフルベッキ夫妻の本来の来日目的であるキリスト教の布教活動(伝道活動)が、おおっぴらに許されるのは10年もの先のことであった。
Ⅲ 人材の宝庫、何礼之英学塾
多士済々の「何礼之英学塾」の主要な塾生として、慶応元年(1865年)の時点における次のような人々の名簿が残されている。
薩摩 前田弘安(前田正名) 原田荘助 白峰駿馬(実は越後長岡出身) 錦戸広樹(陸奥宗光、 実は和歌山出身) 谷村小吉 岸良俊之丞(兼養) 川崎強八 高橋四郎左衛門(高橋新 吉) 鮫島武之助外数十名
加賀 高峰譲吉 芝水昌之進外二十余名
土佐 野村維章 萩原三圭外十余名
肥前 山口範三(山口尚芳) 牟田豊 野田益晴外数名
阿波 高橋顕正(芳川顕正) 山田要吉 高良二(蘭医高良斉の子)
筑前 井上良一 本間英一郎 栗野慎一郎其他
その他、熊本、久留米、柳川、松前等諸藩の藩士、及び地役人の子弟を合わせて百数十名の塾生と塾外生200名が名簿に記載されていたという。
今ここに、塾生として名前を記載された人々は、いずれも明治期日本社会において画然たる働きをした人々であるが、その中の数人について、ここで簡単に紹介しておきたい。
まず「何礼之英学塾」における最大グループ薩摩藩士数十名の一人として、ここに名が挙がった「白峰駿馬」という芝居がかった名前の人物は、元々、鵜殿豊之進という越後長岡藩士であった。
豊之進は、異父兄・鵜殿団次郎を幕臣(蛮所調所教授、後に目付)に登用した勝海舟の門下生となり、長岡藩を脱藩して神戸海軍操練所に参加する。
白峰駿馬こと鵜殿豊之進は、神戸海軍操練所の解散後は坂本龍馬が結成した亀山社中・海援隊に加わり、同社が運用する帆船太極丸の船将として活躍した。
明治2年、白峰は菅野覚兵衛(坂本龍馬の義弟)と共にアメリカに留学、ラトガース大学やニューヨーク海軍造船所で造船術を学び明治7年帰国して明治11年から白峯造船所を経営した。
後年アメリカに永住し、消化剤として有名なタカジアスターゼや、あらゆる手術の止血剤として用いられるアドレナリンの抽出という世界的発明を遂げた高峰譲吉は、加賀藩御典医である父からも西洋科学への探求を進められて幼少から外国語と科学に才能を見せ、加賀藩から選ばれて長崎に留学した。
塾の新校舎が棟上げをした慶応元年(1865年)、何礼之塾で薩摩藩に次いで二十余名が塾生となっていた加賀藩士の筆頭とでも称さるべき高峰譲吉は、年齢わずか12歳の俊秀であった。
佐賀藩の山口尚芳は明治元年3月、外国事務局御用掛拝命を皮切りに、他の明治政府顕官の殆どがそうであったように、慌しく様々な官職につき、明治6年の遣欧使節団には大久保利通、木戸孝允、伊藤博文と並ぶ副使に任命された。
その後明治8年には元老院議官、明治14年には初代会計検査院長に、明治20年には高等法院陪席裁判官に就任、明治23年貴族院議員に勅撰された。
阿波藩の芳川顕正は、山県有朋の側近として知られた人物で、司法大臣、文部大臣(2回)、内務大臣(3回)、逓信大臣(2回)を勤め、その後大正6(1917)年に辞職するまでの5年間、第4代枢密院副議長を務めた。
最後に筑前(福岡)藩士・井上良一、本間英一郎、栗野慎一郎について言及し、次章に移りたい。
福岡藩第11代藩主黒田長溥(ながひろ)によって長崎留学を命じられたこの三人のうち、井上と本間は、その後福岡藩初の藩費海外留学生としてアメリカ留学を命じられ、1869(明治2)年、ボストンに到着した。
この時、井上良一は16歳、本間英一郎は15歳であった。
アメリカ合衆国は、5年に亘り60万人の戦死者を出した内乱(南北戦争)が終わったばかりであり、この時以後、工業化、都市化が力強く推進されて、30年後には工業生産高においてイギリスを抜き、世界首位に立つに至る。
井上はその後ハーヴァードで法律を、本間はマサチューセッツ工科大学で土木工学を、それぞれ学んで共に卒業し、明治7年に帰国した。
帰国後、本間は海軍省、京都市に勤務の後、明治13年工部省鉄道局に入って、敦賀線、長野線(アブト式鉄道を採用した碓氷線)等の工事を責任者(所長)として担当した。
一方、井上は、明治10年4月発足した東京大学法学部における唯一人の日本人教授として採用された。
当時の東大法学部は英語で英米法を教えて、政治学、経済学は文学部で教えられていた。
法律に関して言えば、この頃、司法省法学校においては、フランス語でフランス法が教えられており、井上良一と同じ頃ハーヴァード大学法科を卒業した勝海舟の女婿・目賀田種太郎とそのアメリカ留学時代の仲間である相馬永胤らが、明治13年創立した専修学校(専修大学の前身)は、初めて「日本語で法律や経済を教える学校」として、満天下の注目を集めるという状況であった。
ところが、26歳で東大法学部教授に嘱任された井上良一(よしかず)は、不幸なことに明治12年1月、発作的自殺を遂げてしまった。
余談ながら、講道館の創始者にして長い間(23年余)東京高等師範学校(筑波大学の前身)の校長を務めた嘉納治五郎は、東大文学部第2期生(政治学、理財学専攻)として、新進気鋭のフェノロサ教授から理財学(経済学)と政治学の指導を受け、明治14年に卒業した。
その上嘉納は、フェノロサの人格とその言説に傾倒し、ハーヴァードで専ら哲学を専攻していたフェノロサの「哲学講義」を受けるために、明治14年、東大文学部哲学科に学士入学を果たし、併せて審美学の選科にも入って明治15年卒業し、学習院に奉職する。
本題に戻ると、「何礼之英学塾」の名簿に記載された上記の人々の事績については、この小論で到底語りつくせるものではないが、敢えてここに福岡藩士・栗野慎一郎に言及して、次の話に移りたい。
福岡(筑前)藩槍術師範の長男に生まれた栗野慎一郎は、慶応元年(14歳)に藩費留学生として長崎に遊学、前記井上や本間と共に何礼之の私塾に塾生として名を連ねていたが、長崎市中で福岡藩士がイギリス水兵を斬殺するという事件が発生してその嫌疑を受け、京都六角の獄に繋がれてしまった。
別に犯人がいて、無実の栗野は明治2年釈放されたが、明治4年岩倉使節団の一員となった福岡藩第12代藩主黒田長知に随行してアメリカに留学した福岡藩士金子堅太郎や、団琢磨らの仲間に加えてはもらえなかった。
その後栗野は東京に出て、めげることなく英語修行に励み、明治8(1875)年、ついに藩費(県費?)留学生としてアメリカに派遣されてハーヴァードに入学する。
ハーヴァードでは法律を学び、丁度同じ時期にハーヴァードで法律を勉強していた金子堅太郎や小村寿太郎と親交を結び、同じくボストンにあるマサチューセッツ工科大学で鉱山学を学んでいた団琢磨とも交遊を深めたという。
小村寿太郎は飫肥藩からの大学南校貢進生であり、大学南校改め開成学校の秀才として明治8年、第一回文部省派遣海外留学生として選抜され、鳩山和夫ら7名と共にアメリカに留学したのであった。
栗野も金子も団も、福岡藩校修猷館の出身であり、団琢磨は帰国後は大阪専門学校(第三高等学校の前身)や東京大学理学部で教鞭を執るが、すぐに工部省鉱山局技師に転出、明治21年、三池鉱山が明治政府から三井に売却されると、三井三池炭鉱社事務長に就任、周知のように、その後三井財閥の総帥となった。
さて明治14年、ハーヴァードを卒業して帰国した栗野慎一郎は外務省に入省、井上馨外務大臣の下で働き、明治19年には翻訳局次長を勤めていたが、不平等条約改正案をめぐって青木周蔵外務次官と衝突して退官する。
幸運にも、栗野はすぐに榎本武揚逓信大臣に拾われて逓信大臣秘書官を拝命、逓信省では参事官や外信局長を歴任、明治23年にはパリにおける万国電信会議の日本代表を勤めた。
幸運には幸運が重なり、明治24年、榎本武揚が外務大臣に就任、栗野は外務省政務局初代局長に任命された。
明治27年、陸奥宗光が外務大臣に就任すると、栗野慎一郎は駐米公使兼メキシコ公使として渡米、愈々国際場裏における日本外交の最前線での活躍がはじまる。
明治29年には駐イタリア公使兼スペイン公使に、翌明治30年には駐フランス公使に任命されてパリに赴任した栗野は、そこで日本公使館付駐在武官・明石元二郎陸軍大佐と出会う。
13歳年下の明石元二郎は母校修猷館の後輩であった。
明治34年、駐露公使に転任しペテルスブルグに赴任した栗野慎一郎は、ここで再び、算術と語学に長けた駐在武官・明石元二郎大佐の上司として職場を同じくすることになった。
最近放送されたNHKの特別番組『坂の上の雲』では、あまり噛み合わない両者の関係が描かれている。
朝鮮半島を含む北東アジアの支配権(権益)をめぐって、ロシアと日本の対立が沸点を迎えつつある時、キャリアー外交官栗野慎一郎は、その人生における正念場を迎えつつあった。
明治37年2月6日、ハーヴァード在学中から親交のあった小村寿太郎外相の訓令により、栗野はロシア政府(ラムスドルフ外相)に「国交断絶通知書」を提出した。
これに対してロシアは2月9日に宣戦布告し、日本は翌10日に宣戦布告したが、その宣戦布告文を起草したのは、わずか36歳にして外務省政務局長に抜擢された修猷館の後輩・山座円次郎であるという。
日本は日露戦争に勝利し、フランス公使館が大使館へ昇格した明治39年1月、栗野慎一郎は初代駐フランス特命全権大使に任命され、その後明治44(1911)年8月、栗野大使は日仏通商航海条約の調印を果たして日本は関税自主権を回復し、幕末以来の「不平等条約」は、ようやく改正されるに至った。
前述したように、明治8年3月1日、横浜租界に進駐していた英仏海兵隊員370名が横浜港イギリス波止場から日本を去って以来、実に36年の歳月が経っていた。
メリケン波止場とか、イギリス波止場という言葉を知っている日本人は、今ではもう殆どいないのではないか。
ペルリ来航以来、天下の人心は一斉に海外に向かい、志の高い少年の理想は長崎に遊学することであった。
その長崎で、長崎奉行所の事務や「官立長崎語学所」の学頭としての任務に従事しながら、英学を志して長崎に集まる諸藩からの数多の俊秀のために、元冶元年(1864年)、「私塾」を開設した何礼之は、この時わずか24歳であった。
何玲之の英学者としての名声を慕って、短時日の間に300余名の塾生が集まった背景には、何自身の学者としての天凜の資質と共に、何を19歳の頃から懇切に指導したアメリカ人宣教師ギドー・フルベッキという、何にとって掛け替えのない恩師であるばかりでなく、「日本近代化における巨大な存在(大恩人)」があったことを忘れてはならない。
Ⅳ 日本近代化の恩人、フルベッキ
フルベッキは1830(文政11)年、オランダはユトレヒトに近いザイストで生まれた。
父カールは村長も務め、地方の名士として尊敬されていたが、内気で素朴な人柄であったという。
8人兄弟の6番目の子として生まれたフルベッキは、幼い頃から教養が高くて信仰の深い父母から良い教育を受けて、謙虚で慎み深く、洗練された紳士に育った。
母アンナ・マリアから詩と音楽を愛する心を受け継いだフルベッキは、ピアノ、オルガンばかりでなくバイオリンやギターも上手に演奏して、日本の人々を驚かせた。
明治20年、旧約聖書の明治文語訳が刊行され、詩編とイザヤ書を翻訳したフルベッキの美しい日本語は、その後の日本文学に大きな影響を与えたとされている。
母から受け継いだ詩人の魂が、図らずも異郷の地日本において花開いたと言うべきであろうか。
幼時はザイストのモラビアンの学校で学んだフルベッキは、18歳頃にユトレヒトの工業学校に進学し、卒業後に短期間ながらザイストの鋳物工場で働いている。
1852(嘉永6)年9月、妹セルマの夫でありニューヨークで牧師をしていたジョルジュ・ヴァン・デュールの勧めに従って22歳になるフルベッキは、新天地アメリカへ渡った。
義弟デュールは、スカンジナビアの貴族出身である牧師オットー・タンクに援助を受けていたという。
宣教師オットー・タンクは、スリナム(オランダ領ギアナ)では伝道活動に止まらず、奴隷解放運動家、鉱物学者、とりわけ企業家として幅広く活動し、靴修繕屋、鍛冶屋、パン屋、惣菜屋、工務店(大工の店)、製材業等を経営していたという。
オランダのザイストで結婚した最初の妻が亡くなり、オットーが再婚した女性キャロラインは、先妻のザイストにおける女学校の学友でもあったが、父親の遺産として莫大な財産を所有していた。
その財産を用いて、ウィスコンシン州にモラヴィア教徒のモデルとなる町(モラヴィア派のコロニー)を建設して、オランダ青年を援助したいというのがオットー・タンク牧師の考えであった。
移民としてニューヨークに上陸したフルベッキは、タンク牧師が立ち上げたコロニーであるウィスコンシン州グリーンベイにあるタンク・タウンの鋳造工場と機械工場で働くという契約をタンクと交わした。
裕福な牧師オットー・タンクは、アメリカにおいても企業家たちと様々な事業に取り組んでいたという。
蛇足ながら付言すればウィスコンシン州グリーンベイは、今アメリカン・フットボールの名門(強豪)チームであるグリーンベイ・パッカーズの本拠地として有名である。
このコロニー(タンク・タウン)での生活は毎朝6時の礼拝で始まり、夜8時の礼拝で終わるという規則正しいものであり、タンクは信徒たちに仕事を与え、ミッションの仕事を手伝っていたが、フルベッキにとっては水に合わないところがあり、転職を決意する。
ニューヨークの妹夫婦のところへ身を寄せて仕事を探すが思うような職がなく、結局アーカンソー州での土木技師としての仕事を見つけ、翌1853年、アーカンソー州へレナに移住したフルベッキは土木工事に従事し、土木技師として橋を建設する設計の仕事を担当した。
ところが、アーカンソーの夏の暑さはオランダ育ちのフルベッキには耐えがたく、ここで南部の黒人奴隷の悲惨な生活にも心を痛め、トーマス・ビーチャー牧師らの奴隷解放の説教を聞きに行ったという。
翌1854(安政元)年夏、ヘレナでコレラに罹って1ヶ月以上病床に伏し、医者への支払いが増える一方、骨と皮ばかりになったフルベッキは、もし病が癒えて健康になったら宣教に身を捧げると神に誓ったという。
回復してグリーンベイに戻ったフルベッキは、タンクの工場の管理を引き受け、1854年の冬と1855年を平穏に過ごしたという。
しかしながら、コレラの羅病体験や孤独の中で、聖職者への転進を考えたフルベッキ(26歳)は、1856年ニューヨーク州のオーバーン神学校に入学し、程なくしてS・W・ブラウン師の助手としてオワスコの教会でドイツ系移民の説教に当り、そこで後に伴侶となるマリア・マニオンと知り合う。
1859(安政6)年2月にフルベッキはオーバーン神学校を卒業したが、折しも長崎在留の先任宣教師から日本伝道の勧告があり、それに志願したフルベッキ(29歳)はブラウン、シモンズと共に選任された。
そして前述したように4月18日、フルベッキはフィラデルフィアの教会でマリア・マニオンと結婚、4月28日にオルバニーでアメリカ市民権を申請するが許可されず、無国籍のまま1859年5月7日にニューヨークを出帆して日本に向ったのであった。
さて、前章までに述べてきたように、フルベッキは元治元(1864)年春から何礼之の要請に応じて何の「私塾」で英語を教え始め、その後長崎奉行の要請に応えて、8月からは官立「長崎語学所」で年俸1200両という破格の待遇で英語を教え始めた。
「語学所」は既述のように慶応元(1865)年には「済美館(せいびかん)」となり、そこに集まった諸藩の藩士はフルベッキの高度な学識と高潔な人格にうたれた。
この頃の長崎には、亀山社中・海援隊の坂本龍馬、長州の高杉晋作、木戸孝允、伊藤博文、井上馨、佐賀藩の大隈重信、薩摩の小松帯刀、西郷隆盛、従道兄弟や、何礼之の「私塾」にも塾生として名を連ねている薩摩藩士・錦戸広樹こと陸奥宗光らが、様々な立場や思いを背負って昼夜を問わず、縦横に動き回っていた。
そういう背景において、佐賀、薩摩、土佐、長州、加賀、福井の各藩が、フルベッキを藩の学校の教師として招聘したいと申し出たが、フルベッキは自らの宣教師としての使命を考えて全て辞退したという。
ところがフルベッキに断られても諦めない人物が一人いた。
フルベッキこそ「日本近代化を指導する不可欠の教師」と見込んだのか、佐賀(肥前)藩士・大隈八太郎(重信)は、そのフルベッキを是非とも佐賀藩校の校長に招聘すべく、絶妙の対策を練り上げたのであった。
佐賀藩には元々「弘道館」というれっきとした藩校があり、大隈や一歳年下の久米邦武も、そこの秀才である。
しかしながら、「武士道と云ふは死ぬ事と見付けたり」という言葉で知られる「葉隠」の地に、外人校長を迎えるようなことは思いもよらず、仮にそんな事を口にすれば、「西洋かぶれの大隈」は、たちまち暗殺の対象となって落命したであろう。
当時27歳前後の大隈八太郎の打った手は、正に絶妙と評すべきものであった。
その対策のキーストーン(要石)とでもいうべきか、フルベッキを校長に頂く学校の「学頭」になってもらうために、大隈が説得したのは自分より10歳年長の副島(旧姓枝吉)種臣であった。
副島は佐賀藩随一の秀才として知られ、藩主鍋島直正(閑叟)の覚えもめでたい人物である。
その上、副島の父である枝吉南濠は、国学者として藩校「弘道館」の重鎮であり、兄の枝吉神陽も国学者として弘道館で教鞭を執り、水戸の藤田東湖と並ぶ「二傑」と称されていた。
1865(慶応元)年1月、ついに大隈らの努力が実り、長崎に佐賀藩校蕃学稽古所が正式に設立され、10月10日には名称を「致遠館」と改め、校長フルベッキ、学頭・副島種臣という体制で、日本最初の近代的な大学教育の基礎が築かれたのである。
この頃「済美館」と兼務であったが、フルベッキは時間の大半を校長である「致遠館」に割いた。
フランス語その他も教える「済美館」と異なり、「致遠館」は英語だけの専門学校であり、学頭副島種臣は猛烈に英語を勉強して短期間で初級クラスを終え、教師の一員になったという。
「致遠館」の英語初級クラスは小出千之助を筆頭に、石丸虎五郎、馬渡八郎、大隈八太郎(重信)が教えていて、フルベッキは初級をマスターした生徒に中級英語を教えるかたわら、大隈ら教師たちに対しては高度の英語を指導し、教材として「聖書」や「アメリカ合衆国憲法」を用いた。
因みに1788(天明8)年制定の「アメリカ合衆国憲法前文」には次のような文言が記されている。
「われら合衆国の人民は、より完全な連邦を結成し、正義を樹立し、国内の静穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由の祝福のつづくことを確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために憲法を制定する」(宮沢俊義編『世界憲法集』)
当時フルベッキが、ニューヨークの改革派教会海外伝道主事フェーリスに依頼して、12ヶ月もかかる船便ではなく60日で届く郵便船(パシフィック・メール)で、「致遠館」に送付してもらった教材を紹介すると次のようなものである。
学校用のテート著 自然哲学(48冊)
商業辞典(4冊)
民法(6冊)
刑法(6冊)
ウェーランドの経済原論(12冊)
ダナ編、ホイートン著 国際法(3冊)
ウルゼーの国際公法(6冊)
統計学の標準的な図書(6冊)
ストーレーの合衆国憲法釈義(3冊)
合衆国憲法(小冊子)(60冊)
上記のような原書が英語で学ばれていた「致遠館」は、後の世の日本の多くの大学を上回るアカデミック・レベルにあったと言えよう。
長崎での10年間、フルベッキにとってはキリスト教の伝道を開始することが大きな夢であり、フルベッキ夫妻の来日目的もそこにあった。
ところが依然として禁圧下にあるキリスト教の直接的布教は困難であり、そういう状況においてフルベッキが手がけたのは、まずキリスト教に直接関係のない欧米の書籍を知識欲旺盛な日本人に販売することであった。
次に、熱烈な求めに応じて英語を教える中で、ヨーロッパの文化と近代思想の啓蒙のための教材としてフルベッキが選択した書籍が、英語や漢文に翻訳された「新約聖書」と、「アメリカ合衆国憲法」であった。
オランダ語を母国語とするフルベッキは、ドイツ語を最も得意とし、英語、フランス語を自由に操る語学力を駆使する上に、哲学、文学、法学、経済学、工学、物理学、天文学にまで及ぶ幅広い知識と教養を備える類稀な教育者であった。
更にフルベッキは後述するように、きわめて優れたバランス感覚の持ち主でもあり、かてて加えて口の堅い人物であることによって、岩倉具視その他明治政府首脳部から絶大の信用を得ることになる。
短期間とはいえ、幕末の長崎に存在した「済美館」、「致遠館」という二つの学校は、その後の日本の近代化をリードする数多の俊秀を世に送り出したが、その代表的人物の一人が大隈重信である。
後年、大隈八太郎(重信)は、フルベッキからキリスト教と算術を学んだと語っているが、『早稲田大学百年史』には次のように記されているという。
「フルベッキなくして大隈なく、大隈なくして早稲田大学なし」
Ⅴ 何礼之とその門弟・前島蜜
文久3年、23歳にして英学者として独立を果たした何礼之が、翌元治元年、「私塾」を開設して、そこに忽ち諸藩から300余名の塾生が集まったが、長崎奉行所の事務にかかわり、官立「語学所(済美館の前身)」学頭を務めながら、そのような大塾を一人で運営するには無理がある。
そこで何は、フルベッキに上級者の指導を依頼し、同時に「塾長」として、後年「日本郵便の父」となった前島密を任命し、前島は専ら下級者の指導に当った。
何礼之より5歳年上の前島密は、1835(天保8)年、現在の新潟県上越市に300年続いた豪農・上野助右衛門の次男として生まれ幼名を房五郎といったが、生まれてすぐに父が病没、4歳からは高田藩士の妹であった母てい(貞)と共に上野家を出て高田に移る。
母からは詩歌の暗記のほか、錦絵や往来物で教育を受け、7歳のとき、母と共に叔父の糸魚川藩の藩医・相沢文仲に養われ、医学を志すようになる。
「栴檀は双葉より芳し」という言葉があるが、糸魚川藩士・銀林玄類に医学の古典を学び、後に竹島俊司などに書や茶事を学んだ房五郎は、10歳になると母と別れ、高田に遊学、藩の儒学者・倉石典太の塾で学んだ。
そして驚くべきことに、1847(弘化4)年、わずか12歳の房五郎はオランダ医学を学ぶために単身江戸に向ったのである。
江戸ではまず、一関藩士都沢徹の塾生になり、後に開業医・上坂良庵の学僕となり、翌年(13歳)には幕医・添田玄斎の薬室生から同じく幕医・長尾全庵家の食客となることができた。
かくして医学修行の道には何とかしがみついたが、学僕とは名ばかりで、薬室、患者に関わることは殆どなく専ら薪水の労を執ることが務めで、寒い冬の夜は十分な夜具もなく、寒さで眠ることができないような厳しい生活が3年続いたという。
房五郎の財布はいつもカラで、たまに母親がしつらえて送ってくれる着物も、転売して借金の支払いに当てるような有様で、本人の言をそのまま借りると、「寒苦は骨に入り 貧窮は洗うが如かりし」という状況であった。
ところが16歳の頃、水戸浪士桜井某や日本橋の書店の主らの知遇を得て、政治、兵法などの書籍を筆耕して収入を得られるようになった上野房五郎は、そのお陰で兵式や西洋事情等を知識とするようになっていた。
そうこうする内に1853(嘉永6)年、ペリー提督が軍艦4隻で来航、18歳の上野房五郎は、接見役・井戸石見守の従者の一人として浦賀に赴くという思い切った行動にでた。
「小使たる若年の好僕を雇入るべし」という噂を耳にした房五郎が、口入業者に本心を明かして頼み込んだ結果であった。
従者として接見役・井戸石見守のそばで、ペリー本人やアメリカ海軍の将卒、そして黒船をまじかに見て一大決心をした房五郎は、翌1854(安政元)年、19歳にして「国防考察」のために、全国の港湾を視察して回ったのである。
北陸道、山陰道を経て、下関から船で豊前小倉に渡り、九州西海岸を経て長崎に至り、肥後、日向を経て四国に入る。
四国は伊予、讃岐から紀伊に渡り、伊勢から船で三河に渡る。そこから東海道を東上して伊豆、下田に至り、船で江戸に帰った。
19歳の若者が陸路を行く時には野宿をしてまで、このように果敢な(向こう見ずな?)行動をした理由を、後年その自叙伝において前島密は次のように述べている。
凡そ実地を知らずして論策するは、恰も盲者と夢を談ずるよりも愚劣なり。
方今最も急務とするは国防なり。
我は無識といえども、豈徒に座して読書に日を銷せんや、宜しく起て実地を見、以て大策を建言すべきなりと決心し、自己を顧みずして血気に駆られて奮然たり。
これは、ペリー来航をめぐる周囲の人々の黒船対策の議論が余りにも現実知らず(時代遅れ)のバカバカしいものであることへの苛立ちと、アメリカ海軍をまじかに見て、世界の大勢、実態に目を開いた青年・前島密の「志士的肌合い」を最も端的に示す言葉ではないか。
辞書を開くと、「志士」とは、「命を投げ出して国家・民族のために尽くそうという高い志をもつ人」となっている。
一方、前島は血気に逸るばかりでなく、冷徹な一面をも示す次のような言葉を述べている。
余は既往に顧み深思するに、余のこれまでになしたる行動は、徒に血気に駆られて盲動せしに過ぎざれば、向後は謹慎勉学せざるべからず。学なくして盲動するは、実に狂者の所為なりと、痛く自ら戒むる所ありし。
こういう反省のもと、翌1855(安政2)年、20歳を迎えた上野房五郎は、友人西村某等の紹介斡旋により旗本・設楽弾正の屋敷に身を寄せる(移り住む)ことが出来た。
設楽は林大学頭の親戚であり、その蔵書を読ませてもらうことが狙いであったが、そこで二度ほど設楽の兄・岩瀬忠震に接するという幸運に恵まれ、英語の必要性を痛感したという。
幕末三傑の一人とも評され、この年、外国奉行としてロシアのプチャーチンとの日露和親条約を締結した37歳の外国奉行・岩瀬忠震(ただなり)は、上野房五郎に対して次のように述べたと言う。
凡そ国家の志士たる者は、英国の言語を学ばざるべからず。英語は米国の国語となれるのみならず、広く亜細亜の要地に通用せり。且英国は貿易は無論、海軍も盛大にして文武百芸諸国に冠たり、和蘭の如きは萎靡不振、学ぶに足るものなし。
かくして上野房五郎の英語志向は、福沢諭吉の蘭学から英学への転換よりも4年先立ってはいたが、当時の江戸には英語のテキストもなく英語教師も容易には見つからず、房五郎が英語を学ぶのは後述するように数年後、長崎においてであった。
当面、上野房五郎最大の関心事は、外国へ行くための外洋航海船、しかも帆船ではなく「蒸気船」となり、1857(安政4)年、22歳となった上野は、幕府所有の日本最初の木造蒸気船「観光丸」の運用長・竹内卯吉郎に機関学を学ぶことになった。
勉強ぶりと人物を気に入られたのか、竹内の好意と手引きで、上野は幕府軍艦教授所の生徒に加えてもらい、観光丸に乗船することができたという。
蛇足ながら日本最初の木造蒸気船・観光丸は、オランダ国王から徳川将軍への贈り物であった。
翌1858(安政5)年、23歳の上野房五郎は巻退蔵と改名し、箱館に向う。
途中、財布や紹介状を失くしてしまうという若さ故の失敗もあって、東北東海岸をわずかな旅費で辛酸を舐めながら青森に辿り着いた。
そこで10日間、船待ちする宿賃にも窮して、篤志家の援助を得て何とか乗船することができた文無しの巻退蔵は、ようやく箱館に到着する。
箱館に来た目的は、幕府諸術調所(開成所)所長の武田斐三郎に就いて、富国強兵のための貿易を支える商船界興隆の道を探り、その端緒としての航海術を学ぶことにあった。
精強な海軍と、並行する商船界の興隆とが、富国強兵への道であることを巻退蔵は強く認識していたからである。
巻は栗本鋤雲に武田の紹介を依頼し、その紹介で面会に訪れた巻退蔵の人物を見抜いた武田斐三郎は、快く自ら主宰する塾への入塾を認めてくれた。
四国は大洲藩出身の武田斐三郎(あやさぶろう)は、緒方洪庵の適塾に入って塾頭を務め、その才能を買われて幕臣に取り立てられ、箱館に10年間滞在し、日本初の洋式城郭「五稜郭」の設計者として有名である。
その後明治新政府の下で、武田は陸軍大学教授、陸軍士官学校主任教授、陸軍幼年学校初代校長を務めた人物であり、上野房五郎改め巻退蔵は、航海術に止まらず、武田から多くのことを学んだのではないか。
机上で航海術を学んだ巻退蔵は、翌1859(安政6)年、箱館丸に乗り込み約7ヶ月間、日本を周回し、測量を行う航海実習に出た。
箱館丸は、初めて日本人によって設計製造された日本最初の洋式帆船であり、二本マスト、船の長さ35メートルの同船レプリカが、現在、函館市内に展示されている。
航海実習の成績が良かったのか、翌1860(万延元)年、25歳の巻退蔵は箱館奉行の命により箱館丸測量役として、約3ヶ月の航海を行った後、江戸に帰ってきた。
25歳にして機関学と航海術を習得した巻退蔵は、間もなくそれを生かして、船乗り(蒸気船機関士長)あるいは機関学指導者のような道に入りかけるが、それとは全く異なる道に彼を導き、後年、巻退蔵改め前島密が、近代国家日本の国家的プロジェクト(郵便制度、鉄道敷設等々)の設計図を引く大役を担うことができたのは、長崎における「英学修行」と、それを指導した宣教師ウィリアムズ、同フルベッキ、とりわけ自宅に寄宿(居候)させてまで巻に英語を指導してくれた5歳年下の「長崎英語稽古所(済美館の前身)」学頭・何礼之との出会いであった。
第Ⅱ章で言及したように、1861(文久元)年3月1日、ロシア軍艦ポサドニックが対馬に投錨して、いわゆる「ロシア軍艦対馬占領事件」が発生した。
既述のように、現地からの急報に接して、時の長崎奉行岡部駿河守長常は長崎奉行所与頭・永持亨次郎を派遣して退去交渉に当らしめたが、この時通訳として随行を命じられたのが、長崎奉行所のエース通訳とでも呼ぶべき21歳の何礼之であった。
既述のような経緯により同年9月、ロシア軍艦は乗員360名と共に対馬を退去し、事件は解決したが、その後始末に同年10月対馬に出向いた外国奉行・野々山兼寛一行の中に、外国奉行支配組頭・向山栄吾郎(黄村)の随行員・巻退蔵が入っていたのである。
向山黄村は養父の職を継いで箱館奉行支配組頭となり、のち外国奉行支配組頭、目付にも取り立てられた開国論者であり、当時としては飛びぬけて学識の高い人物の一人であった。
一行は、函館奉行とロシア総領事との決議に基づきロシア海軍の造営物を破壊し、向山らは12月に、野々山らは明けて文久2年正月に、長崎経由で江戸に帰った。
ところが巻退蔵は向山黄村一行と共に江戸には戻らず、自らの5回目の訪問となる長崎の地で、かって外国奉行岩瀬忠震から受けたアドバイスに従ってか、遅くとも文久2年の初めから宣教師ウィリアムズらに就いて「英学修行」を始めたのである。
既に万延元年(1860年)から継続的にフルベッキの指導を受け、長崎における日本人通訳のエース的存在である何礼之と、西洋医学を志し、越後から単身12歳で江戸へ出て、辛酸を重ねて機関学、航海術を習得し、英学修行を始めた巻退蔵が、諸藩の俊秀ひしめく幕末長崎で、知り合い、昵懇となるに時間はかからなかったのではないか。
そして1863(文久3)年、年も押しつまって二人の関係が決定的となる出来事が起った。
この年11月、何礼之は、池田筑後守長発が率いる「遣欧使節団」またの名を「横浜鎖港使節団」一行に通訳として随行するよう江戸幕府から命じられたのである。
従者を必要としていた何礼之に対して、「彼国の実況を概見したしと、熱望して」、巻退蔵は5歳年下の何礼之の従者となり、二人は筑前藩(福岡藩)所有のコロンビア号で江戸へ向った。
ところが既述のように、同船は機関から蒸気が漏れる等の故障が頻発して、江戸へ着いた時には、使節団はフランス軍艦モンジュに乗船して既に横浜を出港していた。
翌1864(元治元)年早々、二人は空しく長崎に戻り、その後間もなく何礼之は既述のように官立「英語稽古所」学頭兼務のまま、新たに「何礼之英学塾」とでも呼ぶべき「私塾」を開設する。
フルベッキを教授に招いて上級者の指導を依頼し、巻退蔵(29歳)を「塾長」として初心者の指導を任せた何礼之は、そこに至るまで短期間ではあるが巻にマンツーマンの英学特訓を施し、時にそれは午前2時に及ぶことがあったという。
巻の英語力は語学の天才何礼之の特訓によって飛躍的に向上し、英語初心者の指導を任せられるレベルにまで到達した結果の「塾長」任命であろうが、何よりも少年時代から前記のような試練に耐え、天凜の資質を遺憾なく発揮して志士的な気概に溢れている巻退蔵という人物を、何礼之はきっちりと見抜き、絶大の信頼を寄せたのではないか。
何礼之英学塾は、何礼之の名声を慕って開設早々から塾生は数十名を数え、塾長とはいえ巻退蔵自身は何礼之の自宅に寄宿(居候)するという境遇の中で、巻は自分と同じように資力が足りず勉学に困難を感じている者の為に、何礼之の承諾を頂いて、崇福寺の境内に「培社」という寄宿舎を設けた。
程なくして、この何礼之塾の外郭のような英学生合宿所「培社」の学生である薩摩藩士・鮫島誠蔵から巻に対して思わざる申し出があり、それは開設したばかりの鹿児島開成学校の英語教師として巻退蔵を招聘したいという薩摩藩の意向であった。
巻退蔵の前島は、もともと学究となる気はなく、英学も未熟と、ただちに鮫島の要請に応ずる気はなかったが、後任が見つかるまでのことで、長逗留は強いないという再三の説得と、薩摩藩人となって後に、どこへ遊学するも巻の勝手という懇切な招聘に心が動き、元治元年10月には何礼之の承諾を得ていた巻は、慶応元年正月14日、何の自宅で雑煮を頂き快く送り出されて、薩摩藩の汽船で鹿児島に向った。
鹿児島での受講生が増えたため、巻は助教として長崎の塾生の中からから安保清康(後に海軍中将男爵)と橘恭平(後に神戸郵便局長)の二人を選んで鹿児島に呼び寄せ、何礼之やフルベッキから短期間に集中的に学んだ英語力を生かして指導に励み、薩摩藩受講生からも慕われたようである。
このようにして、薩摩藩開成学校英学教師としての生活を1年近く送った巻退蔵は、慶応元年12月には、兄・上野又右衛門の死去を理由に、休暇をとって故郷新潟に、そして江戸に帰った。
鹿児島では、家老小松帯刀や大久保利通ら、薩摩藩の指導的立場にある人々に何度も招かれて談論の機会があり、薩摩を去る時には受講生から深い惜別の情を寄せられた巻退蔵ではあったが、その後鹿児島に戻ることはなく、江戸に暮らし、慶応2(1866)年3月、幕臣の前島家をついで、前島来輔(後に密)となった。
巻退蔵である前島密は、前述したように元々政治家的な志士肌の人物であり、語学の学習の如きは世界の大勢を知る方便に過ぎなかったと言えよう。
一方、薩摩藩士の中には可愛さ余って憎さ百倍というべきか 、休暇から戻ってこない前島を裏切り者扱い(暗殺の対象?)にする者もあったようであるが、前島はしばらくの間、江戸市中で小さな英・漢書の塾を開き、そこに当時17歳の星亨が入門する。
前島密と星亨、そして何礼之との関係については後に詳述したい。
そうこうする内に1867(慶応3年)年、幕臣前島密(32歳)は幕府開成所数学教授を拝命した。
少年時代からの西洋医学、機関学、航海術の修行の最後に、長崎の宣教師フルベッキによって数学に磨きをかけられた結果であろう。
そして同じく慶応3年7月、前島の恩師である「済美館」学頭・何礼之(27歳)も、江戸幕府に抜擢されて幕府開成所英学教授並に任命され、長崎を引き払って江戸に出てきた。
余談になるが、何礼之と前島密が教鞭を執った幕府開成所は一ツ橋門外の広大な「護持院原(現在の千代田区神田錦町)」にあり、その後明治新政府に接収されて開成学校となった。
明治新政府の下で学制はめまぐるしく変わり、名称は三転四転したが、開成学校は結局明治10年、東京大学法文理の三学部となり、写真に示す「学士会館」脇の記念碑がそのことを示している。
東大が現在の本郷キャンパスに移転したのは、明治17,8年になってからのことであった。
文部省布達によって学制が敷かれた明治5(1872)年、東京は第一大学区第一番中学のアメリカ人教師ホーレス・ウィルソンが同校生徒にベースボールを伝えたが、明治6年、第一番中学は開成学校(後期開成学校とも呼ばれる)と校名が変わり、さらに明治10年には開成学校改め東京大学となったのである。
同じく「学士会館」敷地内の、写真に示すユニークな彫刻が、「日本野球発祥の地」を示すものである。
東大文学部第2期生の嘉納治五郎は、ここでベースボール(野球という言葉は明治20年代後半に生まれた)を知り、自分がベースメン(内野手)やフィールダー(外野手)ではなく、ピチャーであったことを後年楽しげに回想している。
本題に戻ると、長崎を引き払って江戸に出てきた何礼之は、息つく間もなく慶応3年11月、幕府海軍所軍艦役主格、海軍伝習生徒取締に任命される。
かくして、校主(塾主)が江戸へ引き抜かれてしまった「何礼之英学塾」は開設後わずか3年にして消滅してしまった。
しかしながら、北は松前藩から南の薩摩藩まで、洋学を志して長崎に集まった数多の俊秀を収容した何礼之の「私塾」は、そこに在学した人々がその後の日本社会において果たした画然たる役割を思う時、幕末蘭学における緒方洪庵の適塾、福沢諭吉の慶応義塾にも劣らない成果を挙げたと、評価し得る「私塾」ではなかったか。
後述するように、何礼之と前島密、そしてフルベッキが、江戸改め東京で、日本近代化のために果たした役割は絶大なものである。
そして、何礼之は単なる語学の天才、日本のエース通訳ではなく、歴史家・大久保利顕がいみじくも喝破したように、「西洋学啓蒙学者」として、後述するように「日本近代化」に特筆すべき大きな役割を果たしたのであった。
そして、何礼之や前島密が幕府開成所の教官に抜擢されて2年後の1869(明治2)年2月、「何礼之英学塾」にも在籍した前記山口尚芳が明治新政府の使者として長崎を訪れ、フルベッキに対して、学校設立のために東京に出仕するよう要請した。
招聘に応じたフルベッキは、明治2年4月から幕府開成所改め開成学校の語学及び学術の教師となり、翌明治3年10月から、開成学校改め大学南校の教頭に就任する。
写真に示す神田錦町(旧護持院原)の開成学校キャンパス内に宿舎を与えられたフルベッキが、馬で外出する時には同じく馬に乗った2,3人の護衛が付き従い、開成学校のフルベッキ以下「御雇外人教師」を野蛮な(?)日本人の襲撃から護るために、同校には常に20人の護衛が勤務していたという。
前述したように、フルベッキは「済美館」教授として長崎奉行所から破格の待遇を受けていたが、明治新政府によるフルベッキに対する待遇は、それを遥かに上まわって破格なものであった。
明治7年ごろの日本人官吏の月給は、太政大臣三条実美800円、右大臣岩倉具視600円、参議大久保利通500円、外務少輔山口尚芳300円というものであったが、大学南校教頭ギドー・フルベッキの月給は600円であった。
<続く>
参考文献
大久保利顕著『幕末維新の洋学』 2007年 吉川弘文館刊
大久保利顕 「幕末英学史上における何 礼之―とくに何礼之塾と鹿児島英学との交流―」
『地域研究所研究年報第6報』 1977年 鹿児島県立短期大学地域研究所編
薮内吉彦 「幕末における長崎での前島密の活躍―何礼之・フルベッキとの英語師弟関係を中心
に―」 『郵便史研究第32号郵便史研究会紀要』 2011年9月 郵便史研究会編
前島密著 『前島密自叙伝』 1997年 日本図書センター刊
日野清三郎著 長正統編 『幕末における対馬と英露』 1968年 東京大学出版会刊
赤城毅 「クリミア戦争の世界史的意義について―バルト海・ギリシャ・東アジアにおけるクリミア戦
争についての考察―」
『上越社会研究第10号』 1995年8月 上越教育大学社会科教育学会刊
伊藤一哉著 『ロシア人の見た幕末日本』 2009年 吉川弘文館刊
池田史郎著 池田史郎著作集刊行会編 『佐賀藩研究論攷 池田史郎著作集』
2008年出門堂刊
週刊江戸 No.67 「長崎を震撼させた3日間―フェートン号事件―」
ディアゴスティーニ・ジャパン2011刊
大橋昭夫 平野日出雄著 『明治維新とあるお雇い外国人―フルベッキの生涯―』
1988年 新人物往来社刊
伊藤典子著 『フルベッキ、志の生涯―教師として宣教師として』 2010年 あゆむ出版刊
W・E グリフィス著 松浦玲監修 村瀬寿代訳編 『新訳考証 日本のフルベッキ―無国籍の宣教師
フルベッキの生涯―』2003年 洋学堂書店刊
参照ウェブサイト
PDF 『長崎唐通事何礼之の英語習得』 許 海華(XU Haihua)
FROM THE HISTORY OF RUSSIA'S PACIFIC FLEET DEFENNSE OF PETROPAVLOVSK
近代史のファイル―ボストンの侍・井上良一
フリー百科事典ウィキペディア;
Fleetwood Pellew;フェートン号事件;トラファルガーの海戦;佐賀藩;クリミア戦争;日露和親条約;カティーサーク;ロシア軍艦対馬占領事件;ナヒーモフ;白峰駿馬;高峰譲吉;山口尚芳;芳川顕正;本間英一郎;栗野慎一郎
|
|