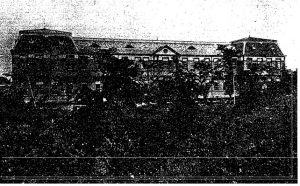昭和の大剣士・<剣聖>高野佐三郎
―恩人・嘉納治五郎と共有した教育理念(中)
Ⅳ 流派を超えた統合組織体「大日本武徳会」
Ⅳ—1 「武徳会」生成・発展の時代背景
『明治剣客伝』の著者・戸部新十郎氏がいみじくも指摘したように、明治維新後の「衰退期」を経て興隆してきた剣術は、いずれ流儀流派を超えた統合組織体を必要としていた。
警視庁を頂点とする警察関係に籍を置く名人・達人たちは、それぞれ小野派一刀流、北辰一刀流、神道無念流等々を名乗っているが、さほど変わりのない打突方法や打突部位をもって試合をしている現状から、統合、統制は自然の成り行きでもあったが、実際の統合組織団体の誕生は、思わざる二つの要因によってもたらされたのであった。
それは、明治28年が平安遷都千百年に当たり、かって日本の中心都市であった京都市が、その記念行事を大々的に行うべく、かねて計画を進めていた事柄から図らずも発生したのである。
まず第一に、平城京から長岡京へ、そして10年足らずで平安京(京都)へと遷都した桓武天皇を祝い祀るべく、平安朝の昔をしのぶ「大極殿」を、当時の二分の一に縮小して岡崎の地(現・平安神宮の地)に再建しようというものであった。
この時、京都府収税長であった鳥海弘毅が、「そもそも桓武天皇は、武威のかたである。禁裏に武徳殿を設けて武術を奨励され、奥羽、蝦夷の地まで平定なされた。天皇をお祀り申すのなら、武術大会を催すにしくはなし」という追加提案をしたのである。
この考えに賛同する者が増え続ける中で、有志が何度も協議を重ねた結果、武術大会は一度で終わらせてはならないこと、その為にも「大極殿ならぬ武徳殿を建てる」こと、という結論を得たという。
そして遂に首都が東京に移ってから沈滞気味の京都が、「遷都千百年祭」と「内国博覧会」とに沸いた明治28年4月17日、「大日本武徳会」の設立発起人総会が京都待賓倶楽部に於て開催され、満場一致で会の設立が決まった。
総裁には小松宮彰仁親王(陸軍参謀総長)が、会長は渡辺千秋京都府知事、副会長は壬生基修(みぶ もとやす)平安神宮宮司という陣容で、1,武徳殿の新築 2,武徳祭並びに「武術大会の毎年開催」の二つの事項が決定されたのである。
第一目標の「武徳殿建設」は明治31年6月、「大極殿北西の一画に武徳殿あり」の故事にのっとり、忠実に平安神宮北西の地に起工され、東西二十間、南北二十五間の殿堂で、中央に演武場、北方正面に玉座、周囲に参観席が設けられた建物は、翌明治32年3月には竣工した。
そういう準備の上で第二目標たる第一回の武徳祭、ならびに武徳会主催による一大武術大会が、内国博覧会終了直後の明治28年10月に挙行される。武徳祭は25日、平安神宮で執行され、武術大会は26,27,28の三日間に亘り、博覧会工業館跡地に仮設した演武場で行われ、全国から馳せ参じた武術家は989名、そのうち剣術試合の参加者は320名に達し、その中の15剣士が選ばれて総裁小松宮から最高の称号としての「精錬証」が授与された。「精錬証」とは明治35年制定の「武術優遇令」によって「範士」「教士」の称号が設けられるまでの武徳会唯一の称号である。
続いて第二回武徳会大会が翌明治29年10月に行われ参加剣術家は460名を数え、1万2千名の武徳会員が参観して第一回にならい新たに15名に「精錬証」が授与され、その中に本編の主人公・高野佐三郎がいた。
武徳会発足から4年後の明治32年には会員数88万人余、義金(寄付金)も80余万円に達し、武徳殿の建築費ほか諸経費を支払ってなお、本部基金は30余万円という潤沢な財政状況で、その後も順調に発展した「大日本武徳会」は明治42年には財団法人化され、会員数151万人、基金18万円の大団体になっていた。
このように武道の統合組織体として、「大日本武徳会」が財政的にも極めて順調なスタートを切ったについては、前述したように二つの大きな要因があった。
一つは既述のように、平安遷都千百年を祝うに際し、奈良からの遷都を決した桓武天皇の「尚武の天皇」としての事績を祀る記念行事が企画されたことであり、その記念行事を担う「武道団体」の設立が求められたことにあった。
第二の要因は、この時代特有の時代背景としての「日清戦争」である。
二百数十年も鎖国を守っていた日本が、自ら「対外戦争」を仕掛け、初めて国際社会に顔出しをした「日清戦争」は、様々な意味で、その後の日本社会に決定的な影響を与えたことを改めて指摘しておきたい。とりわけ明治28年4月23日、日本国が被った三国干渉(遼東還付)という「国辱的事件」は、その後の日本社会全体の雰囲気(精神的底流・国民感情)を決定的に変えるものであった。
明治27年7月、日清戦争が勃発し、日本人が「眠れる獅子」と恐れた清国は意外に脆く、戦争は一年足らずで日本陸海軍の勝利に帰した。
3年前、「親善」を名目に(実は日本を恫喝する目的で)来日した丁汝昌提督が率いる世界最新鋭の清国北洋艦隊6隻が横浜入港の前に、ご丁寧にも21発の礼砲を発射し、開闢以来聞いたこともない「鋼鉄製戦艦大口径砲」の轟音の凄まじさに、相模湾一円の日本人は腰を抜かしたという。
「定遠」「鎮遠」という、日本人がそれまでに見たことも聞いたこともない「世界最大の鋼鉄製軍艦」を主力とする清国北洋艦隊の壊滅は、日本海軍に大きな自信を与え、「黄海海戦」に勝利した連合艦隊司令長官・伊東祐亨提督の名は、「ヤール―(黄海)の伊東」として世界中に鳴り響いた。
しかしながら、日本の連合艦隊の主力となった戦艦「松島」「初島」橋立」等は、フランスの造船所で建造され、清国北洋艦隊の主力である世界最大級の鋼鉄製戦艦「定遠」「鎮遠」は、ドイツ(現ポーランド)のフルカン造船所で建造されたものであったことを忘れてはならない。八幡製鉄所の発足は明治34年になってからのことであり、日本が鋼鉄製軍艦を造れるようになったのは、日露戦争が終わってしばらく経ってからである。
明治28年4月17日、下関市の料亭・春帆楼において、大日本帝国弁理大臣伊藤博文(内閣総理大臣)、同じく大日本帝国弁理大臣陸奥宗光(外務大臣)と大清帝国欣差頭等全権大臣李鴻章と大清帝国欽差全権大臣李経方(欽差大臣、李鴻章の甥)とによって、下関条約(日清講和条約)が締結され、朝鮮国の独立、台湾、遼東半島、澎湖諸島等の割譲及び賠償金3億両(テール)等が決定する。戦勝気分に沸く日本国民は、各地で提灯行列を盛り上げながら、同条約によって獲得した台湾や遼東半島等における「植民地経営」に夢を馳せる。
ところがその6日後の明治28年4月23日、ロシア帝国、ドイツ帝国、フランス共和国の駐日公使たちが連れだって外務省を訪れ、病気療養中の陸奥外相に代わって応対した林董外務次官に対し、日本の遼東半島領有は東アジアの平和を乱すものとして、「遼東還付を勧告する覚書」を手渡す。
これを「青天の霹靂」として、日本の新聞各社は事実を国民にどう伝えるべきかわからず茫然自失、しばらくの間、右往左往の体であった。
結局、この三国を相手に戦う能力は日本にはなく、日本政府は5月5日の閣議で全遼東半島の放棄を閣議決定し、同日、その旨を独露仏駐日公使に連絡する。米英、米露、英仏、英露、露仏の間では「大使」が置かれている中で、日本と欧米各国との間には「公使」のみが置かれている時代のことであった。明治28年11月8日には北京に於て「遼東還付条約」が締結され、日本は遼東半島は失ったが代償金(賠償金)として清国から洋銀3億両(テール)を得る。
5年賦とはいえ洋銀3億両(テール)は、当時日本の国家予算の4倍に匹敵する大金である。
そういう大金(喧嘩の落し前?)を得て財政的に大いに潤った日本では、財政難を理由に中断していた官費留学生の海外派遣が再開され、秋山真之海軍大尉(海兵17期)はアメリカへ、広瀬武夫海軍大尉(海兵15期)はロシアへ、それぞれ留学した。だが、この巨額賠償金の支払いは、清国知識人に大きな衝撃と屈辱感とを与えたことを記憶しておきたい。
「取らぬ狸の皮算用」となった「遼東還付」に関するこの一連の始末は、日本国民の自尊心を大きく傷つけ、新聞の見出しも「遣る瀬無き悲憤」等々の悲壮な言葉に溢れ、やがて巷では「臥薪嘗胆」等のスローガンが叫ばれ、日本社会全体が国粋主義的、軍国主義的雰囲気に覆われていく。
設立当初、武徳会の目的は、「武道ヲ奨励シ、武徳ヲ涵養スル」とされていたが、明治32年になると、「専ラ武術ヲ以テ心(胆)ヲ練磨シ、廉恥ヲ重ンジ、節義ヲ励ミ、一朝有事ノ時ニ当タリテハ、君国ノ為メ、死ヲ見ル羽毛ノ如キ精神ヲ養成シ、以テ国家ノ元気ヲ振興セントスルニ在リ」という風に全く軍国主義、全体主義の風潮に染まっていった。
折しも李鴻章との交渉(買収?)に成功した北京駐在ロシア公使カシニ伯爵は明治31年、「旅順港、大連港租借に関する露清条約」を締結して、日本が涙ながらに諦めた遼東半島に鉄道や港を設置することに成功、ロシアは念願の「不凍港」を手にする。
「取らぬ狸の皮算用」どころか、「トンビにアブラゲをさらわれる」ことになって、豊臣秀吉の朝鮮戦争以来、300年も対外戦争の経験が無く、初めての外国との戦争(日清戦争)に勝って有頂天になっていた日本国民は、頭から冷水を浴びせられ、煮え湯を飲まされた感じとなり、列強(独露仏)によるこのような仕打ちによって巷には悲憤慷慨する人々が溢れた。こういう時代背景の中に生成発展した「大日本武徳会」であり、こういう国民感情(世論?)の行き着く先は、「臥薪嘗胆」等々の悲壮な覚悟と、列強との対決であった。
余談ながら付言すると、前駐清ロシア公使カシニ伯爵は、この「露清条約締結」という大手柄を認められて駐米大使に栄転、ワシントン駐在各国外交団の首班にも推されて、その令嬢はワシントン社交界の花と称えられる存在となっているうちに、日露戦争という事態に遭遇する。
貴族的、高圧的なカシニ伯爵は、大国ロシアの大使として(新興国アメリカを見下して)国務省に出かけて行き、ヘイ国務長官を怒鳴りつけるような態度がアメリカ人にも不人気で、結局、日露講和条約交渉が始まる直前に、ロシア政府もアメリカ世論を慮ってか、その更迭を余儀なくされた。
Ⅳ―2 「武徳会柔術試合審判規定」の成立
さて、上記のような時代背景において、その基本精神に軍国主義的タガが嵌った「大日本武徳会」ではあったが、諸流派を超えた統合組織体が出来れば、どうしても必要なものとして「試合審判規定」と、「形」という二つのものが求められるのは当然である。
明治32年、大日本武徳会は、柔道は嘉納治五郎が委員長となり、剣道は大浦兼武(当時の警視総監)を委員長として、それぞれ「策定委員会」をつくり、「武徳会柔術試合審判規定」「武徳会剣術試合審判規定」を作成するに至った。
まず敢えて先に柔道に注目すると、「武徳会柔術試合審判規定」策定の為の嘉納治五郎を委員長とする「策定委員会」の委員には講道館から山下義韶、横山作次郎、磯貝一の三名と、大東流の半田弥太郎、四天流の星野九門、楊心流の戸塚英美、良移心頭流の上原庄吉、起倒流の近藤守太郎、竹内三統流の佐村正明、関口流と楊心流とを兼ねた鈴木孫八郎という顔ぶれの人々が参集した。
数十年、あるいはそれ以上、何代にも亘って継承されてきた百流を超えるとされる柔術諸流の中で、創業17年目の嘉納治五郎(40歳)を委員長(盟主?)と仰いだ、当時の柔術家の潔い態度も賞さるべきであろう。
改めて総括すれば、前述したように嘉納治五郎の創意工夫、即ち「武術の競技化(スポーツ化)」という世界的イノベーション(技術革新)の中身(講道館柔道)は、当身技の全てと、手首、手指あるいは足首等に対する関節技を排除して、敢えて武術としての実用性を離れたことにあった。
実戦を意識してのことか、既成の柔術家が捨てきれなかった当身技、関節技を思い切って棚上げしたことが、嘉納の成功の核心であった。
「創造的破壊」というプロセスを経た嘉納によるイノベーションの成果は絶大で、元々あった古流柔術の投げ技自体も、講道館システムによる「錬成と洗練」の結果、従前とは比較にならない「スピードと巧緻性そしてパワー(決定力)を有するハイレベルの投げ技」に変貌し、そこで育成された柔道家に既存の柔術諸豪は圧倒されてしまった、というのが実情であろう。
仮に、嘉納が在来の柔術にこだわって、乱取りの中に当身技や手首等に対する関節技を僅かでも含めたとすれば、結果は全く異なっていたことは明らかである。例えば、嘉納治五郎が開発した「浮き腰」から「釣り込み腰」に発展伸張するプロセスを考えてみよう。もし、そういう投げ技の最中に、相手の顔面に対する当身や頭突き、あるいは下腹部に対する膝蹴りや、手首をねじるような動作が許されたならば、投げ技の探究、錬成は不可能となること、火を見るより明らかではないか。
一子相伝あるいは家元制を伝統とする古流柔術各派においては、投げ勝負の乱取りを「稽古体系(練習システム)」の中心に据えることには、ためらいがあったのかもしれない。
その一つの理由として、昔から行われてきた「取り」と「受け」とを決めて一方的に決められた「形」を繰り返す稽古とは全く異なり、「乱取り」稽古の場においては、体格差、体力差に基ずく優劣、強弱は誰の目にも明らかで、指導者が口頭で「権威主義」を押し通せる余地は全く無く、その一方、ややもすれば乱取りは、「ねじくりあい」に陥り、「実力?」以外は通用しないからである。
古流柔術の進化が遅れたもう一つの原因は、柔術家の生活環境にもあったのではないか。
「柔道を通じて立派な人(士)をつくる(養成する)」ことを唯一の目的とした講道館は、明治15年の創立から明治27年までの12年間、入門料不要、月謝不要、一切無料の「極めて純粋な公共教育機関」であり、そこには「何かを教えてその対価を得る」と言うような精神は無かった。これに対していわゆる「町道場」の多くは、弟子たちからの入門料や月謝によって運営されていたことが影響していたとも言えよう。
嘉納の工夫について更に言及すると、技術的な創意工夫(イノベーション)にとどまらず、日本で初めて「修行の場格」として二段、三段等の数字を用いたのも嘉納治五郎であり、嘉納の成功に倣って、剣術界では常用されていた切紙、目録、奥伝等の呼称が無くなり、それまで剣術とか撃剣と呼ばれていたものが、遂には(大正5年)「剣道」に統一されたことも忘れてはならない。
その上、修行者のモチベーションに関しても、在来の「免状」に加えて「黒帯」という誰の目にも明らかな目標を、日本で初めて設定したのも嘉納である。古来「黒白をつける」という言葉があるが、白い稽古着に黒い帯とは、何とも鮮やかな嘉納治五郎の発想ではないか。
Ⅳ―3 「大日本帝国剣道形」成立までの角逐
以上、「武徳会柔術試合審判規定」成立の背景について言及したが、次に本題の剣道に目を向けてみよう。
戸部新十郎氏が指摘するとおり前述の「試合審判規定」と共に、全国で行われる「形」の制定こそが、諸流派を超越した統合武道たる「柔道」及び「剣道」を象徴する出来事であり、明治39年5月、武徳会は柔・剣道の新しい「形」を制定するために予算1千円を計上し7月から、その検討を始める。因みにこの頃の海軍中尉の年俸は400円であった。
柔道は大浦兼武会長から依頼された嘉納治五郎が委員長となって、戸塚英美(戸塚派楊真流)、星野九門(四天流)という武徳会両範士とはかり、諸流の柔術家を委員として全国的に行わしめる「形」を制定する委員会が開催された。嘉納が提案した「講道館乱取りの形」としての「投げの形15本」と「固の形15本」が、ほぼそのまま採用されて「大日本武徳会制定柔術形」となったのである。
一方、剣道は事情が違った。剣道は渡辺昇子爵・武徳会商議員(範士、神道無念流)を主査とする7名の委員が委嘱されて、早くも一か月後の明治39年8月13日、答申案が大浦兼武会長に提出され、小松宮総裁の決裁を経て同年12月下旬、「大日本武徳会新剣術形」として世間に発表された。ところが、この明治39年制定の「大日本武徳会新剣術形」は剣術家の間では不評で、少なからぬ不満が寄せられていた。
そうこうするうちに明治41年、柔・剣道が中等学校の正課に加えられることが決定され、文部省では以後毎年、東京高等師範学校(校長嘉納治五郎)で開催される中等教員講習会に「武道所」を設けたが、その「武道所」会合の席上、講習会の責任者である嘉納治五郎校長が、「剣道」に関しては、より統一的、かつ普遍的な「新剣道形」制定の緊要性を強調したという。
この嘉納の発言は、渡辺昇主査ら7名が明治39年に一か月足らずで、そさくさと決定した「武徳会新剣術形」が普及されない状況から見て、それが中等学校において採用されるには不適当と断定されたことを意味し、武徳会にとっては「面子(メンツ)丸潰れ」とも言うべき事態となったのである。
東京高師校長嘉納治五郎の、こういう発言を受けた武徳会は直ちに調査委員会を設けて新たな「剣道の形」の制定にとりかかる。前回(明治39年制定「新剣術形」)の経緯(失敗)に鑑み、武徳会はあまねく剣道家の納得が得られ、しかも全国的普及をなし得る「形」の制定を第一目標として、全国から25名の委員(剣術家)を選び、その中の高野佐三郎(東京高師)、内藤高治(武徳会本部)、門奈正(武徳会本部)、根岸信五郎(東京代表、神道無念流)、辻真平(佐賀代表、心形刀流)の5名を主査に任命した。
高野ら主査5名は、草案作成のめどを明治45年5月として、京都妙伝寺に籠り連日討論を重ねた。高野によると、「この主査の研究というものは実に熱烈なもので、誠心誠意、命をかけての討論であった。高野佐三郎は、懐に短刀を蔵し、自分の意見が容れられないときは、刺し違えて死ぬ覚悟で、常に会議に臨んでいた」という。
こういう中で草案が練られ、ようやく同年(1912年、大正と改元)10月に至り、京都市大学生集会所で、委員25名による委員会が開催される運びとなった。そこで、草案に基づく「形」が実演されて、大浦会長が議長となって討議が行われ、太刀7本、小太刀3本という今日の「日本剣道形」の原型としての「大日本帝国剣道形」が制定されたのである。その後多少の変化が加えられて今日の「日本剣道形」に伝えられている「大日本帝国剣道形」制定の中心人物・高野佐三郎に対して、武徳会会長大浦兼武は感謝状に添えて、「剣道統一」の文字を揮毫して贈ったという。
「大日本武徳会新剣術形」から「大日本帝国剣道形」が成立していく課程には、中心人物となった東京高師教員(講師)高野佐三郎の活躍と共に、上記のように東京高師校長嘉納治五郎の大きな影響力が働き、正に、「日本体育の父」と称される嘉納治五郎(53歳)の面目躍如とも言うべき場面であった。
これに先立つこと5年、「講道館柔道」は益々充実発展し、明治40年5月には全国師範学校長が、同年7月には全国中学校長が講道館に招かれ、嘉納治五郎によって「柔道の理論及び教育上の見地からの真価並びに教育法」と題する講演と乱取りを含む実演が行われた。
Ⅴ 剣道と教育(学校体育)
Ⅴ―1 アジア初IOC委員・嘉納治五郎
「大日本帝国剣道形」の制定(大正元年)から遡ること3年、既述のように明治42年1月、講道館長にして東京高等師範学校長嘉納治五郎は、駐日フランス大使ジェラールから突然会見を申し込まれ、早速1月16日に嘉納はジェラールと会見する。この会見に於けるジェラールの用件は友人クーベルタン男爵の意を受けてクーベルタンが推進しているオリンピック運動の中で、嘉納に東洋人初のIOC委員就任を要請することであった。
直ちにこの要請を快諾した嘉納治五郎は、外には体育運動を通じて諸外国と交誼を結び、内にはオリンピック競技会で行われている各種スポーツを通じて、国民の体力の増進と「品性の陶冶」とを図ろうと決心したという。
明治42年5月、ベルリンに於けるIOC総会でIOC日本代表委員として嘉納が選ばれ、約2週間後の6月15日クーベルタンは嘉納に書簡を以てその結果を報告した。駐日大使として、多少は日本国内事情を知るジェラールが、なぜ嘉納治五郎を選んだのか、1月19日のクーベルタン宛書簡の中でジェラールは、嘉納についての「打ってつけの人物」という言葉に、フランス語ではなく、わざわざ英語「right man」を用いて、嘉納治五郎が自ら「柔道」を創始したばかりでなく、「多様なスポーツを推進していた」ことを挙げ、同時に嘉納が中等学校教員を養成する日本中等教育の総本山とも言うべき「東京高等師範学校の校長」であることを指摘していた。
更にジェラールがこの書簡の中で、嘉納治五郎推薦のもう一つの特別な理由として敢えて取り上げたのは、嘉納治五郎が「国際的な視野を持っている」ということであった。
学習院教頭、その後の文部省参事官、五高、一高の校長の後、23年と4か月に亘る東京高師(筑波大学の前身)校長(一時は文部省普通学務局長兼務)として、常に教育現場の最前線に立ち続け、嘉納塾塾長や、最盛期には1600名余の清国留学生を収容した宏文学院の院長を務めながらの、年中無休・昼夜兼行・東奔西走の講道館長嘉納治五郎こそ、正に「日本国近代化の申し子」と称さるべき人物ではないか。そのように「天下御免の東京高等師範学校長」であった嘉納が、生涯を通じて最も腐心したのは、既述のように三育(徳育、体育、知育)の併進(バランス)即ち「知育と同じ重みを持つ体育の普及発展」ということであった。
日清戦争勝利の暁に列強による「三国干渉(遼東還付)」という煮え湯を飲まされ、「臥薪嘗胆」等のスローガンが叫ばれる屈辱的10年を経て、「日露戦争講和条約」に至るまで、「明治時代の40年」は、日本国が幕末以来押し付けられてきた「不平等条約」という「半植民地的境遇」を脱するための40年であったとも言えよう。だが、そういう渦の中で、「知識万能主義が瀰漫する日本社会の将来」に対する大きな危機感を抱いていたのが嘉納治五郎であった。
知識万能主義蔓延の結果、「総じて躁急」或いは「熱しやすく冷めやすい」という「日本の国民性の負の側面」が更に助長され、その結果、対外的困難に直面して日本国民が容易に激昂し、排外的ナショナリズムに酩酊するという危険な状況が生じることを嘉納は危惧していたのではないか。
後述するように日本国内に「スポーツ」という言葉もなく、日本人の大多数がオリンピックで行われている「競技」の多くを見たことも聞いたこともないという時代背景において、嘉納治五郎は「明治維新以来の日本の教育における知育偏重の歪みを正す」ために、「知育と同じ重みを持つ体育の普及発展」の道を邁進したことを改めて確認しておきたい。
そして、そういう嘉納治五郎と、「スポーツ」を「自ら努力すること(l’effort libre) 」と定義したクーベルタン男爵とは、洋の東西を隔て互いに何の連絡もなくして、実は「同じ土俵の上」に立っていたことを指摘したい。換言すると、両者共に世界を視野に、夫々の国で、「スポーツを重要な教育手段として位置づける」ことに勇往邁進していたのであった。
Ⅴ―2 クーベルタン男爵がイギリスで発見した教育理念
明治7年、嘉納より3歳年下のクーベルタン男爵フレデイ家の三男ピエールは、この年パリに開設されたイエズス会の中等学校サン・チニャース通学学校(寄宿学校ではない)の第一期生40人の一人として入学した。同校に教師を派遣するイエズス会の基本方針は、「道徳教育こそがキリスト教教育機関の第一の関心事とすべき」というものであった。そのサン・チニャース校においてギリシャ・ラテンの古典文学をほぼ完ぺきに身に付け、抜きんでて聡明な生徒であったピエール・ド・クーベルタン男爵が12歳頃、初めて愛読したのがイギリスの作家トマス・ヒューズ作の『トム・ブラウンの学校生活』であったことは、その後のクーベルタンの運命を暗示するかのようであった。
その物語は、パブリックスクール改革を先導した人物として世界に有名なトマス・アーノルドが校長であった時代のラグビー校に入学した田舎のジェントリー(郷紳)の息子トムが、学校生活(学寮生活)の中で様々な経験を経ながら、逞しい青年へと成長していく姿を描いたものである。
主人公トムがジェントルマンに必要とされる「真の男らしさ(true manliness)」の要件として、勇気、忍耐力、公正さ、友愛の精神といった「徳」を歳月と共に獲得していく課程で体験するクリケットやフットボールといった「スポーツ」、あるいは鳥の巣探しなどの屋外の遊び、更には喧嘩(拳闘)の仕方をも含めて、一つひとつの場面が感動的、教訓的に描かれた作品であったという。
そして17歳になったピエール・ド・フレデイ・ド・クーベルタン男爵は、サン・シールのフランス陸軍士官学校に入学するが、ピエールは入学後数か月でサン・シール陸軍士官学校を退学した。長兄ポールは教皇領護衛隊員であり、サンシールを卒業した次兄アルベールはフランス正規軍の大佐に昇ろうとしていた時である。聖職者となるか軍人になるか、どちらもフランス貴族の男子にとっては天職たるべきものであった。フレデイ家の人々にとって三男ピエールの士官学校中退は、しばし困惑の種であったかもしれないが、「行動と功名を求める」ピエールにとっては、士官学校を卒業しても、その後の単調な駐屯地勤務が目に見えている当時フランスの社会情勢に、我慢する気が無かったのではないか。
明治2年、ピエールが8歳の時、フランスは普仏戦争に惨敗し、ヴェルサイユ宮殿・鏡の間で、鉄血宰相ビスマルクが取り仕切って、プロイセン国王がドイツ皇帝ウィルヘルム1世となる儀式が行われるという、フランス国民にとって何とも屈辱的な事態を招いた。
トラファルガー海戦でひび割れ、ワーテルローの戦いで大きく傷ついたフランス人の「民族的自負心」は、皇帝ナポレオン三世が捕虜になった普仏戦争惨敗によって、木っ端みじんとなってしまったのである。戦後、「柔弱なフランス青少年を鍛える」ために、「学校体育の軍事教練化」や、教室における「詰め込み教育」が励行されて、今度は、その弊害が社会問題となりつつあった。
そういう時代背景の中で明治16年、クーベルタン(20歳)は、数週間をかけてイギリスのパブリックスクール(イギリス以外にそういう教育機関は存在しない中産階級以上の男子生徒を対象とする特有の全寮制中高等学校)として有名なハロー校、イートン校、ラグビー校を訪問して回り、併せてオックスフォードとケンブリッジにも立ち寄っている。続いて明治19年夏、彼は再びイギリスを訪れ長期に滞在し、翌年秋にもイギリスへ渡り、それ以後、毎年渡英したという。
このような行動の中でクーベルタンを磁石のように惹きつけたのがラグビー校と、40年前に死去したそこの校長トマス・アーノルドが自らの教育理念に基づいて敷いた先覚的教育路線であった。
周知のように、アーノルド校長は「知育に偏らない全人教育的な教育原則」を確立した人物として、世界教育史に名を残している。
イギリス教育改革の実践者ラグビー校校長トマス・アーノルドに対する熱い思いと、綿密な視察を基に、ついに明治20(1887)年 クーベルタン(25歳)は フランスの雑誌『社会改革(La Reforme Sociale)』に「イギリスの教育」という論文を、翌明治21年には「イギリスにおける教育」という、いずれも画期的な論文を掲載するに至った。
普仏戦争惨敗という事態を受けてフランス文部当局が、「柔弱なフランス青少年を鍛える」ために打ち出した「学校体育の軍事教練化」や教室における「詰め込み教育」の弊害を憂慮して、25歳の若者クーベルタンは、「彼らは知識を詰め込まれ、生き字引にされて疲れ果て、その知性ばかりを太らされ、体力(force physique)と精神的エネルギー(e’nergi morale)は奪われている」と訴えたのである。そして 上記二つの論文によって、「フランスの教育システムに欠けていた理念」を、イギリス教育の中に発見したことを主張したのである。それは「百年戦争」以来の「親英」「嫌英」「反英」等々、数百年に亘るフランス国民のイギリスやイギリス人に対する「国民感情のうねり」を超越しての、クーベルタン男爵の人類史に輝く快挙と評すべきであろう。
更に、その主張の中で、「スポーツ」を「自ら努力すること(l’effort libre)」と定義したクーベルタンは、その論文「イギリスの教育」冒頭に、フランスの高僧オルレアン司教フェリックス・デュパンルー(アカデミー・フランセーズ40人終身会員の一人)の、次のような言葉を引用していた。
教授(instruction)は知識を与え、精神を満たし、物知りを作る。
教育(education)は資質を発展させ、魂を高め、人間を作る。
フランスではこの二つの言葉が混同され、instructionばかりでeducation が皆無であると指摘したクーベルタンは、かくして弱冠25歳にして、「スポーツを中心とする身体活動を重要な手段とする教育の普及」に自らの貴族としての使命を見出し、「(若者の)魂を鍛えるものは他には(スポーツ以外には)ない」ということを、世界の人々に最も効果的に提言して「近代オリンピック」開催への道を拓いたのである。
Ⅴ―3 明治時代日本のスポーツ事情
御一新(明治維新)以来、鉄道その他インフラは発達し、寺子屋や藩校に代わる「学制」も整備されて、ベースボール、テニス、蹴球(俗称サッカー)、陸上競技、ボート競技等が高等教育機関を中心に「輸入」され、普及されつつはあったが、大多数の日本国民のメンタリティーは徳川時代と殆ど変わらず、1920(大正9)年に至っても、スポーツを「遊戯」と翻訳して、さほどの違和感を持たなかった。
一例を挙げると、大正9年発行の雑誌『野球界』(第拾巻第九号)は、アメリカ中西部の名門シカゴ大学野球チームと共に来日したシカゴ大学(市俄古大学)教授(野球部長)メリーフィールドの「遊戯の道徳観」と題する談話を掲載したが、その談話(論文?)の冒頭には何と「スポート(Sport 以下遊戯と譯す)の趣味は誰にもある」と記されていたのである。
因みにこの年(大正9年)、シカゴ大学野球チームを率いて来日した上記シカゴ大学教授(野球部長)フレッド・メリーフィールドは、シカゴ大学野球部の名投手(主将)として活躍し、その後恐らく神学校を卒業して、キリスト教伝道の為に来日、北部バプティスト派が運営する東京学院(現・関東学院大学の源流、当時は市ヶ谷に校舎があった)の教師(宣教師)をしていた。
明治37年、そのメリーフィールドは、ある人に紹介された安部磯雄(篤いクリスチャン)の 依頼によって、創部3年目の早大野球部でコーチをすることになったという。容姿端麗、人格温厚なメリーフィールドはコーチとしてひとたびグラウンドに立つと、傍で見ている安部野球部長がハラハラするほどに厳しく猛烈に、早大選手を鍛えたようである。俗に、「田舎の三年、都の昼寝」という諺があるが捕球動作その他、本場の一流選手であったメリーフィールドのコーチングによって、草創期の早大野球部は多くのものを得たか、瞬く間に一高・学習院・慶應という当時の最強チームを破ったのである。
明治時代、「運動競技」という言葉は日常茶飯に使われていたが、sportに匹敵する日本語はなかった。明治から昭和まで「身体之教育」、「身体教育」、「遊戯」、「体操」、「教練」、「体練」等の言葉はあったが、欧米に於けるようなスポーツという「言葉(概念?)」が日本にはなかったのである。
civilizationを「文明」、speechを「演説」と翻訳したのは福沢諭吉であり、scienceを「科学」、philosophyを「哲学」と翻訳したのが、徳川幕府派遣留学生としてオランダのライデン大学等で4年間学んだ西周であったように、それまでこういう言葉が無かった日本社会に、スポーツという言葉(概念?)が無かったのは当然とも言えようか。大正9年に至ってもsportを「遊戯」と翻訳していたのである。
そしてその「スポーツ」という言葉が日本で初めて使われたのが明治44年ないしは明治45(1912)年になってからのことであった。「スポーツ」という言葉を日本で初めて使用したのは、安部磯雄早大教授兼野球部長兼監督兼マネージャーが引率した「日本スポーツ界初の海外遠征」としての早大野球部米国遠征団(第一回)の主将(遊撃手)を務め、早大文学部を卒業後改めてアメリカで4年を暮らして帰国、ジャーナリスト(新聞記者)となった橋戸信(橋戸頑鉄)であると言われている。
あやふやな日本語ではなく、sportをスポーツとして初めて使用したジャーナリスト橋戸頑鉄は、日露戦争最中の如何にも破天荒とも言える企てとなった「早大野球部米国遠征団(第一回)」の主将を務め、帰国後(明治38年)に恩師安部磯雄教授の勧めもあって『最近野球術』(博文館刊)を出版した。「日本野球の進歩に大きく貢献した一冊である」と言われるその著作の巻末に、「米国の野球界」と題する論文を掲載した橋戸(26歳)は、その中で日本野球界が「非科学的練習」、「向こう見ずの練習」をしている愚を嘆いたように、開明的(科学的・合理的)な見識と進取的精神の持ち主として、橋戸頑鉄は当時日本スポーツ界に於ける抜きん出た存在であった。
橋戸が活躍した時代(大正・昭和)からやや遡って、明治から大正にかけての日本国の「スポーツ事情」あるいは「体育事情」を最も象徴的に示している出来事が、前述した井口あくり女子高等師範学校(お茶の水女子大学の前身)教授と、永井道明東京高等師範学校(筑波大学の前身)教授兼女子高等師範学校教授のアメリカ留学体験である。
既述のように、明治38(1905)年11月、38歳の姫路中学校長永井道明は、「体育研究のため満三年間欧米留学を命ず」という文部省からの辞令を受け取り、翌明治39年1月から女子校であるボストン体操師範学校に客分(guest)として入学し、校長ミス・エミー・ホーマンズ女史の厚意で、宿舎として彼女の自宅にお世話になって1年余り、昼夜兼行・東奔西走の体育修行に没頭した。
日中は師範学校の勉学実習、あるいは病院に於て医療体操を、学科は生理、解剖、教育心理などを習得し、夜はYMCA,YWCA、YMCU、市立体育館、市立浴場(プール?)等々、日本では見たことも聞いたこともない施設の見学や実体験に、永井は土日も休みなく精励する。
女子校であった同校は永井が卒業して間も無く、名門ウェルズレー女子大学に合併されてウェルズレー女子大学体育部となったが、永井の客分としての特別修行も卒業と認められて1907年の卒業生名簿にその名前が記載され、帰国後の永井が受け取る書簡には時々、事情を知らないアメリカ人から宛名として永井道明嬢(Miss Michiakira Nagai)と記されているものがあったという。
「収穫多大のアメリカ体育修行」を終えた永井は、イギリス経由でスウェーデンのストックホルムに到着し「国立中央体操研究所」に入学、明治41年7月、同研究所における研修を終了して、前述したように帰国前にストックホルムにおいて東京高等師範学校教授兼女子高等師範学校(お茶の水女子大学の前身)教授の辞令を受け取ったのであった。
歴史を振り返ると戊辰戦争終結後、西洋列強に取り囲まれながら近代国家を目指した日本国は、三条太政大臣を頂点とする古めかしい政治制度を続けざるを得ず、西南戦争に代表される旧勢力の反乱や「明治14年の政変」等々の政治的プロセスを経て、ようやく明治18年12月22日、「内閣制度」が発足して初代内閣総理大臣に伊藤博文が就任する。
同時に教育制度も改められ、明治19年公布の「帝国大学令」により「東京大学」は「帝国大学」となり、更には同時期に発布された「師範学校令」により「尋常師範学校」と区別される「高等師範学校」が制度化されて、既存の東京師範学校は「高等師範学校」と改称改組され、全国唯一の中等学校教員養成機関(全寮制で生活費も支給される官立学校)として、小学校教員の養成に当たる尋常師範学校の校長や教員の養成を担ったのである。
やや間をおいて明治30年、「師範学校令」に代わる「師範教育令」の公布により、「高等師範学校」は尋常中学校・高等女学校・師範学校など広く「中等学校全般の教員養成機関」としての位置が定まり、明治35年に「第2の高等師範学校」が広島に設立されると、「高等師範学校」は「東京高等師範学校」と改称された。
Ⅴ―4 剣道の父・高野佐三郎
明治41年3月19日、「体育に関する建議案」が衆議院を通過し「撃剣・柔道」が中等学校の正課となることが決定し、中等学校教員を養成する東京高等師範学校の嘉納治五郎校長は撃剣科講師の人選を指示する。
一説によると嘉納は内藤高治を望んだというが内藤は武徳会に職が定まっていて、嘉納の誘いを丁重に断った為、嘉納は部下の東京高師剣道部長・峰岸米造教授に人選を任せたという。峰岸は当時高名な剣士たちを順次招いて実際に学生を指導してもらったという。
そこで高野佐三郎は、いつもと変わらず学生たちに猛烈な稽古をやらせたが学生たちは心服し、直ちに高野佐三郎(45歳)が最適任者として明治41年3月31日、東京高等師範学校講師に任命され、4年後の大正5(1916)年に至り、同校教授にまで昇進する。
どこの学校(高等教育機関)も卒業せず、剣道一筋で東京高師教授に上り詰めた高野も立派、そういう処遇を与えた校長嘉納も立派と言えよう。
余談ながら、この時の高野採用の直接的責任者であった剣道部長・峰岸米造(37歳)は、小学校教員の検定試験に合格し、16歳で群馬県桐生小学校の訓導兼校長となった人物である。
その後、群馬師範学校を経て高等師範学校(嘉納治五郎が校長)を卒業、明治31年、母校・高等師範附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)教諭となり、後に高等師範学校教授を兼任して教科書「西洋略史」や「日本略史」を著す。
さて、永井道明がストックホルムにおいて東京高師教授・東京女高師教授の辞令を受け取った明治41年、東京高師の講師に任命された高野佐三郎は同年、東京工業高等学校(東京工業大学の前身)剣道師範に、翌々明治43年には早稲田大学剣道部講師に就任し、大正2年には曹洞宗大学(駒澤大学の前身)剣道師範に、同年中に、陸軍外山学校剣道師範と陸軍士官学校剣道師範にも就任して、幅広く高いレベルの学校剣道の発展に力を尽くす。多忙の高野を説いて早大剣道部講師に招聘した時の早大剣道部主将笹森順三は、後に国務大臣・小野派一刀流第16代宗家として活躍し、高野に率いられた早大剣道部は昭和6年と13年の二度に亘ってアメリカ遠征を果たしてアメリカ在住有段者との試合等を行っている。
前述したように、中等教員養成機関の頂点に立つ東京高師の教授・高野佐三郎は大正4年、学校体育のための剣道指導カリキュラムとも言える「剣道基本教授法(集団指導法)」を考案し、剣道教育史における歴史的名著『剣道』を出版したのであった。
名著『剣道』について、筆者が大保木輝雄埼玉大学名誉教授(日本武道学会会長、剣道教士7段)から頂いたコメントは、「『剣道』という本は高野佐三郎を取り巻く俊才(富永堅吾、山本長治、佐藤卯吉など)との合作とみるのが妥当だと思っています。当時の状況としては剣道の集団指導法の提示が喫緊の課題であったと思われます。高等師範学校の面目にかけて出版されたものと思います」というものである。
高野佐三郎を取り巻く俊才の一人として大保木名誉教授が挙げた佐藤卯吉(剣道範士・九段)は、大正8年、東京高師体育科(剣道専攻)を卒業、引き続き同校専攻科に入り教育哲学を専攻する。卒業後は同校助教授に就任、恩師高野佐三郎の退官後は、剣道主任教授として学生指導に当たった。
敬虔なクリスチャンであった佐藤卯吉は東京剣道連盟理事長、日本剣道連盟理事・評議員として剣道界に貢献し、その死の直後、関係者により佐藤の遺稿は『永遠なる剣道』(昭和50年 講談社刊)として出版されている。
高野自身は「自分がもし、東京高師に職を奉じてなかったら、人間としての今日の私はなかったであろう。学校で多くの教授や先生方に接して刺激を受け、また立場上、勉強し、修養をせざるを得なかった。まったく学校のおかげである。ありがたいことだ」と常に述懐していたという。(戸部新十郎著『明治剣客伝』)
東京高等師範学校長嘉納治五郎は日頃から「科学的」という言葉を口癖のようにしていたと言われるが、科学的に剣道を解明し、普及、指導しようとした高野佐三郎の基本的態度は、高野自身の次のような言葉で表明されている。
「従来の研究法は、数十年来、ありきたりの方法で、多くは師の口授口伝により、自ら経験工夫を積むほかはなかったのである。斯道の書物も、伝書類をはじめとして、はなはだ雑駁な不十分なものばかりで、書物の数も少なく、秩序を立て、体裁を整え、充分に考えて述べられた組織的研究というものは、まったく欠けていた。斯道の技術に秀でた人は、古来沢山あるが、理論的、組織的研究は少しも出来ていない。
申すまでもなく、今日はなにもかも科学的に研究していかねばならない時代である。とくに剣道が、身体、および精神の鍛錬というような点に、いっそう重きを置かれるようになったので、いままでよりはさらに研究すべき範囲も広くなってきた。生理・衛生の智識も入る。心理・倫理・教育の方面にも暗くてはならない。わが国の歴史・国民性等の問題にも関係する。
とくにわれわれは多数の青少年を教育するという重大な責任をもっているのであるから、自己の技倆、すなわち腕を磨くと同時に、理論的、すなわち頭を養うことが、はなはだ大切であろうと思う。(以下略)」(戸部新十郎著『明治剣客伝』)
高野佐三郎が出現するまで数多の剣豪(名人・達人あるいは剣聖)が存在したが、このような視野・視点を持った剣豪は存在しなかったと言うことが出来よう。いわゆる「剣豪小説(物語)」の殆どは、個人が自己の腕(技量)を磨き、精神(心)を鍛える話に尽きるのではないか。(続く)
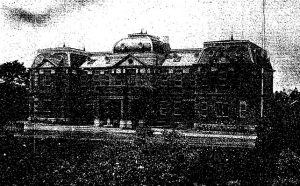
明治39年頃の東京高等師範学校前景
(国立国会図書館デジタルコレクション「東京高等師範学校一覧」より)