 |
 |
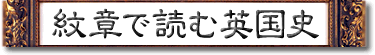 |
| 丸屋 武士(著) |
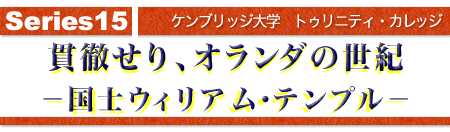 |
 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

フーゴ・グロチウス像
(デルフト市 新教会前広場)
(2004/12撮影) |
| オランダ名ハイフ・デ・フロート(グロチウスはラテン語風の名前)は自治都市デルフトの市長も務めた学識ある都市貴族の長男として1583年に生まれた。11歳でライデン大学に入学し、14歳で数学、哲学、法律に関する論文を提出して大学を卒業。15歳の時ホラント州法律顧問(オランダ連邦共和国の首相的存在)ヨハン・ファン・バルネフェルト率いるフランス訪問使節団に随員の一人として参加した。フランス国王アンリ4世は少年グロチウスの才能を「オランダの奇蹟」と賛嘆し、この旅行中オルレアン大学から法学博士の学位を授与される。帰国後(16歳)、ハーグで弁護士を開業して名声を博した。1613年ロッテルダム市の法律顧問に就任、オランダ独立最大の政治的功労者とされているバルネフェルトの右腕となる。1618年、本編の主人公ウィリアム3世の祖父フレデリック・ヘンドリックの異母兄であり時のオランダ連邦共和国総督オレンジ公マウリッツの政治的判断によってバルネフェルトや仲間2人と共に逮捕された。1619年5月グロチウスは終身禁固刑に、バルネフェルトは斬首刑に処された。72歳のバルネフェルトはビネンホフ宮殿前の処刑台上に立ち「祖国の友よ。私が反逆者でないことを信ぜよ。私は祖国を愛してこの生涯を生き抜き、祖国を愛してここに死ぬ。」と言って、共和派(議会派)対オレンジ家というオランダという国の宿命的な政争の中で、泰然自若として斬首された。2年後、グロチウスは妻と下男の差し入れた書物運搬用の箱に身をひそめて投獄されていたルーフェンステイン城を脱獄、そのままフランスへ亡命した。妻マリア・ファン・レイベルスベルフは男まさりの決断力と機略の持主であった。「私はどのキリスト教国でも、野蛮人も恥じるような無軌道な戦争が行われているのを見る。わずかの原因で、また全然原因がないのに武力に訴えるのが常である・・・」という書き出しの『戦争と平和の法』をパリで出版したのは1625年(寛永2年)のことであった。この書によってグロチウスは「国際法の父」と呼ばれている。その後ドイツへ亡命、晩年はパリ駐在スウェーデン大使を務めたが、外交官としては不向きであった。1645年夏、ストックホルムからの帰途、海難事故によって死去。遺体はオレンジ家の人々も眠るデルフトの新教会に葬られた。 |
|
軍艦やそれに伴う近代産業を作り上げただけで西洋文明を摂取したように錯覚するようでは如何にも甘く、軽薄である。その後の日本は「夜郎自大」の風潮に水をさす者もなく、30年後には「無条件降伏」という破局を迎えるに至った。「夜郎自大」の行きつく先は「孤立化」であるが、それに水をさすどころか、そのお先棒をかつぎ、尻馬に乗る者が大多数で、孤立から袋叩きへの道を転がっていった根っこにあったものは「軽佻浮薄」というもう一つの悪しき国民性であった。「軽佻浮薄」の最大の問題点は、「希望的観測」と「客観的事実」とを混同して懲りないことである。10年を越える「平成大恐慌」という惨禍に遭遇して、ジャパンアズナンバーワン等の言葉に酔っている者はもういなくなったとは思う。何しろどこへ行っても駅前商店街は軒並み駅前シャッター街と化して、東京の、というよりは日本の目抜き通りと称すべき東京都中央区銀座の表通りにも空地が出現するという惨状である。毎年3万人(神奈川県二宮町あるいは茨城県八郷町の総人口に匹敵する)を越える人々が自殺し、しかもその多くが経済問題を抱えた中高年男性という哀しい現象が6年も続いている。一旦逆巻(さかま)き始めた経済収縮(デフレ)の渦を止めることは容易でなく、長い間有名であった銀行の名前もどこかにケシ飛んでしまい、150年前のカール・マルクスの言い条が迫真性をおびて迫ってくる日本(経済)の現状である。しかしながら、「夜郎自大」という民族的特性(国民性)は、福沢諭吉が指摘する白人の人種的優越感と同じく、容易に治癒しない特有の病気である。今後とも日本国民には、むしろこれを痼疾と見る自戒、戒心が求められよう。孤立化が「いつか来た道」となって袋叩きの憂き目に会わない用心こそが、この国の今後にとって最も肝要である。
ベルリンの壁の崩壊は東欧の多くの人々に自由をもたらしたが、同時に「パンドラの箱」を開けたような状況を生じ、21世紀の世界もまた前途多難である。その上日本は人口減少国家として、国力の総体的劣化を防ぐ戦いの重圧が年とともに増大するという厳しい局面にある。このオランダ話を閉じるにあたり、1590年(天正18年)、『新大陸自然文化史』を著したアコスタの次の言葉をもって結びとしたい。「たとえどれほど文明化していようと、改めるべきところがない民族はいない。同じように、どれほど野蛮な民族であろうと、よいところが全然ない民族と言うものはいない」。 |
| <了> |

ウィリアム1世墓像(デルフト市 新教会内)
(2004/12撮影) |
世界最古の国歌、それはオランダ連邦共和国の国歌Willhelms(ウィルヘルムス − 1568年作詞)である(本文8頁参照)。
労作『イギリス革命』の著者友清理士氏が開設しているウェブサイト「オランダ史資料館」の中で同氏が翻訳したオランダ国歌をここに紹介したい。1番から15番までの長大なものであり、通常(オリンピック表彰式等々)歌われるのは1番と6番であるという。ここでは敢えて筆者の独善で3番と4番を紹介したい。
|
| 3番 |
耐えるのだ
根っから誠実な我が民よ
神は諸君を見捨てはしない
たとえ今諸君が悩まされていようとも
敬虔に生きようとする者は
日夜神に祈る
神が我に力を与え
我が諸君らを助けられるよう
|
| 4番 |
我が命と身代のいっさいを
諸君に拒んだことはない
我が名高き弟たちも
同じ気概を諸君に見せた
弟アドルフ伯は
フリースラントの戦いにたおれた
その魂は永遠のうちに生き
審判の日を待っている |
|
参考文献
『Central Cambridge』 by Kevin Taylor
1994年(CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS刊)
ジャロルド観光ガイド・大学都市『ケンブリッジ』
1998年(Jarrold Publishing Norwich刊) |
|
|
| (2005年7月) |
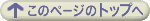 |
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |